人材不足でも勝てる。そんなマーケティング戦略が、従業員5名の零細企業を大手に勝たせました。具体的な事例と実践ノウハウを紹介します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
零細企業がマーケティングで勝つために必要な視点とは
「また人が辞めた……どうやってこの穴を埋めるんだ」
ある日、従業員5人の零細企業を営む佐藤さん(42歳・東京都内でBtoB向けの製造機器を販売)は、デスクに手をついてため息をついていました。
営業も事務も、時には配送も、すべてが兼任。限られた人数で回している会社にとって、ひとり辞めるというのは経営が揺らぐほどの大事件です。
そんな佐藤さんの頭に浮かんだのは、同じ業界の大手企業。人も多く、資金も潤沢。正直、「このままじゃ勝てるわけがない」と感じていました。
しかし、そんな彼の考えを180度変えたのが、私・柳井弘幸との出会いでした。
私は現在、プロフェッショナルマーケティング株式会社の代表として、年間100社以上の中小・零細企業を支援しています。その中で確信しているのは、「小さな会社だからこそ、大手に勝てるマーケティング戦略がある」ということです。
マーケティングに必要なのは、人数や資金だけではありません。
まずは、その本質的な違いを整理してみましょう。
大手企業と零細企業の構造的な違い
大手企業と零細企業では、マーケティングの前提条件が大きく異なります。下記の表を見てください。
| 視点 | 大手企業 | 零細企業 |
|---|---|---|
| 人材リソース | 多い・専門分化 | 少ない・兼任が基本 |
| 意思決定スピード | 遅い(稟議が多い) | 速い(トップが即決) |
| 顧客接点 | 間接的・部門が分かれる | 直接・密な関係 |
| 広告予算 | 数百万円〜数億円 | 数万円〜数十万円 |
多くの人が「人材の少なさ」ばかりに目を向けますが、実は零細企業にはスピード・柔軟性・顧客との距離の近さという明確な優位性があります。
この「構造の違い」を理解することが、戦い方を変える第一歩です。
人材不足を「弱み」ではなく「強み」に変える視点
「人手が足りないから何もできない」
この思考は、成長の大きなブレーキです。
例えば、佐藤さんの会社では、最初はWebマーケティングに取り組む余裕がないと思っていました。
しかし、私は彼にこう提案しました。
「全部をやろうとせず、“今の人数でできる範囲”に絞って、圧倒的に深くやりましょう」
そして実行したのが、以下の戦略です。
- ターゲットを「製薬機器業界の中小工場」に絞る
- 週1回、自社事例を元にした実務寄りのブログ記事を発信
- 営業が訪問した顧客からよくある質問を元に、FAQコンテンツを作成
- リード対応は社長自身が行い、1社1社と深く関係構築
結果として、半年後には問い合わせ件数が2倍、さらにリピート率が70%以上に改善しました。
人材が少ないからこそ、余計なことに手を出さず、一点集中で成果を出す。これが零細企業の勝ち筋です。
✅ 重要なのは「何をしないか」を決めること。
むしろ、人数が少ないからこそ、全員の動きが戦略に直結するのです。
マーケティングは「リソースがある人だけの特権」ではありません。
零細企業でも、むしろ零細だからこそ、勝てる土俵が必ずあります。
次のセクションでは、こうした考え方をベースに、「人材不足を逆手に取ったマーケティング戦略」の全体像を詳しく解説していきます。
あなた:
##人材不足を逆手に取ったマーケティング戦略の全体像 ###絞り込み戦略の重要性と実行ステップ ###スピードと柔軟性を武器にする方法
プロマケSEO記事作成 の発言:
人材不足を逆手に取ったマーケティング戦略の全体像
「人がいないからできない」ではなく、「人がいないからこそできること」に目を向けた瞬間から、零細企業のマーケティングは本当に機能し始めます。
これは理想論ではありません。
実際に、私は数多くのクライアントと一緒にこのアプローチを実践し、成果を出してきました。
では、人材不足を“武器”に変えるマーケティング戦略とは、どのような全体像になるのか?
その核心は「絞ること」「早く動くこと」、そして「顧客と深く向き合うこと」にあります。
ここでは、2つの視点から具体的な戦略と実行ステップを解説していきましょう。
絞り込み戦略の重要性と実行ステップ
まず何よりも大切なのが、「誰に対して、何を売るのか」を徹底的に絞り込むことです。
リソースが限られているからこそ、「みんなに売る」は選択肢に入れられません。
たとえば、以前私が支援した建築系の零細企業(従業員4名)は、最初、一般住宅も店舗内装もリフォームも「全部やります」という方針でした。
でもこれでは、限られたスタッフで回らないし、メッセージも薄くなる。
そこで提案したのは、「飲食店専門の内装工事」に特化する戦略。
結果、以下のような変化が起こりました。
- サイトの訪問者数はそれほど増えていないのに、問い合わせ率が3倍に
- 自社の施工事例が業界内でシェアされるようになった
- 「専門家」として、紹介やリピートが自然に増加
なぜこうなるのか?
「誰のための商品か」が明確になると、届ける言葉も選べるし、相手にも刺さるからです。
マーケティングは、「届ける相手を絞る」ことで、逆に世界が広がるという逆説があるのです。
具体的な実行ステップは以下の通りです。
- 現時点で最も成果が出ている顧客を洗い出す
- その顧客の共通点を分析する(業種・規模・課題・地域など)
- ターゲット層を1つに絞り、そこに特化したメッセージと商品設計を行う
- 発信する情報も、その層にだけ向けてつくる(ブログ、SNS、チラシなど)
✅ ポイントは、広げる前に深掘ること。
この戦略により、少人数でも圧倒的に効率よく「刺さるマーケティング」が実現します。
スピードと柔軟性を武器にする方法
もう一つ、零細企業ならではの強みが「スピード」と「柔軟性」です。
大手企業では、何かを決めるのに複数部門をまたぎ、稟議書を通し、半年かかることもザラ。
その間に市場は変わってしまいます。
一方、零細企業では、社長が決めればその日から動ける。
この機動力こそが、変化の激しい今の時代において最大の武器です。
実際に、ある金属加工の小さな会社(従業員5人)では、取引先のニーズ変化をいち早く察知して、従来の量産型サービスから「1点ものの高単価試作品」へと路線を即変更しました。
この素早い意思決定と現場との距離感が、競合が気づく前に新規案件を獲得する結果につながったのです。
スピードと柔軟性を活かすために必要なことは、以下の3つです。
- 情報が届いたらすぐに意思決定できる体制を整えておく
- 完璧を目指さず、試す→学ぶ→改善のサイクルを回すこと
- 社員一人ひとりが“マーケティング感覚”を持つ文化を育てる
つまり、小さな組織は変化に強いという特性を、戦略の根本に据えるのです。
✅ 「遅いけど大きい」相手と戦うには、「小さいけど速い」武器で勝つ。
これこそが、人材不足を逆手に取る真の戦略です。
マーケティングとは、「どう売るか」ではなく、「誰に、どう価値を届けるか」です。
人が少ないからこそ、「無駄なく、深く、速く」届けることができます。
次の章では、実際に従業員5名の企業が大手に勝った具体事例をご紹介します。
理論が、現実の成果にどうつながったのか。ぜひ、参考にしてみてください。
従業員5名の零細企業が勝った事例
「どうせうちは小さいから無理ですよ」
初回の打ち合わせで、ある精密部品メーカーの社長・藤原さん(45歳)は、そんな言葉を漏らしました。
創業から10年。地道にリピーターを増やしてきたが、ここ数年で大手企業の参入が相次ぎ、既存の得意先が次々と奪われていく。
展示会に出ても、広告を出しても、反応がない。
「もう勝ち目はない」と、あきらめかけていたそうです。
そんな彼が、たった半年で月商を1.5倍に伸ばし、新規顧客の獲得率を3倍にした戦略こそ、まさに人材不足を逆手に取ったマーケティングの実践例です。
その成功のカギを、2つの視点で見ていきましょう。
ターゲット選定と独自ポジショニングの成功要因
藤原さんの会社は、もともと多品種・少量生産が得意でした。
しかし、「何でもできます」というスタンスが仇となり、どんな会社なのか印象がぼやけていたのです。
そこで私が提案したのは、次の問いに徹底的に答えることでした。
- 誰のどんな課題を、うちは本当に解決できるのか?
- 競合ではなく、うちに頼む理由は何か?
現場スタッフともヒアリングを重ねた結果、ひとつの強みが浮かび上がりました。
それは、医療機器メーカー向けの試作加工に異常なほど強いこと。
高精度・短納期・柔軟対応、この3つがそろう会社は他にほとんどない。
そこでターゲットを医療機器メーカーの開発部門に絞り、ポジショニングを明確に定義しました。
ポジショニング=「医療機器業界で“開発スピード”を武器にしたい企業にとって、試作加工の最適パートナー」
この言語化により、以下のような変化が起こりました。
- ホームページを全面リニューアルし、医療機器業界向けに特化
- 成果事例や技術紹介をブログ・SNSで継続発信
- 展示会では「開発スピードで困っていませんか?」という一点訴求
結果、展示会での名刺交換数は前年の3倍。
しかも、その後の商談化率は60%超え。
✅ 「誰のための会社か」が明確になると、相手から選ばれる確率は一気に上がる。
これが、限られたリソースで勝つための差別化戦略の威力です。
顧客との密な関係構築がもたらした効果
もうひとつ、藤原さんの会社が強みとして活かしたのが、顧客との距離の近さです。
大手企業では、窓口が営業、対応が技術、連絡は事務、と分業されています。
そのため、「聞きたいことが伝わらない」「対応が遅い」という不満がよくあります。
一方、藤原さんの会社では、社長自身が営業も技術も対応します。
図面の意図や困っているポイントを、直接ヒアリングして即対応できるのです。
このスタイルは、特に開発フェーズにある顧客にとっては非常にありがたく、結果的にこうなりました。
- 顧客の紹介率が前年比2.5倍に
- 継続案件のリピート率が75%以上に
- 1社あたりの年間売上が平均1.8倍に増加
ある顧客からは、「大手にはできない柔軟さがある」「試作は必ず藤原さんに頼む」とまで言われたそうです。
✅ 関係構築は“対応の速さ”と“共感力”が鍵。
これは、少人数のチームだからこそできる芸当です。
「うちは小さいから勝てない」と思い込んでいる経営者ほど、実は最大の武器を見落としています。
人が少ないからこそ、狭く深く、そして速く動ける。
それこそが、マーケティングにおける大手にはない優位性です。
次の章では、こうした勝ちパターンを仕組みとして回すための「実行体制のつくり方」をお伝えしていきます。
零細企業が実践すべき差別化マーケティング
「どこも同じようなことを言ってる」
それが、顧客の本音です。
同じ商品、同じ価格帯、似たようなホームページ……。中小・零細企業が“その他大勢”に埋もれてしまう原因は、差別化の軸が曖昧だから。
では、大手のような広告予算もブランド力もない零細企業がどうやって選ばれる存在になるのか?
その鍵は、「限定性」「専門性」「ストーリー性」の3つにあります。
そして、それを継続的なコンテンツ発信で可視化していくことが、差別化マーケティングの本質です。
ここでは、実際に成果を出した企業が活用した具体的なコンテンツ戦略と、信頼を築くストーリーテリングの方法を紹介します。
限定性・専門性を打ち出すコンテンツ戦略
まず重要なのは、「自社しか言えないこと」を明確にすることです。
以前、私が支援した厨房機器メンテナンス会社(従業員3名)では、
「どんな業種でも対応します」から
「ラーメン店専門の厨房清掃業者」へと大きく舵を切りました。
この“絞り込み”により、伝えるべきメッセージは一気に明確化。
- 「ラーメン店のスープの脂に特化した独自洗浄液」
- 「換気扇トラブルを未然に防ぐ3ヶ月点検」
- 「夜間対応OK。ラーメン店の営業時間外に作業可能」
こうした専門性ある内容を、ブログ・動画・事例ページ・SNSなどで継続発信することで、ラーメン業界での認知と信頼を一気に獲得しました。
実際、発信を開始してからの変化はこうです。
- ブログのアクセス数が3ヶ月で5倍
- ラーメン関連ワードでGoogle検索3位以内を獲得
- 業界内からの指名問い合わせが毎月5件以上
✅ 専門性は、広く浅くではなく“狭く深く”が勝ち筋。
「この分野ならこの会社」と言われるためには、“限定された世界観”を自ら作り出すことが必要なのです。
信頼を獲得する発信とストーリーテリング手法
差別化は、機能や価格だけでは語り尽くせません。
顧客が最後に決め手とするのは、「この人に任せたい」と思えるかどうかです。
つまり、信頼の醸成。
ここにおいて効果的なのが、ストーリーテリングです。
たとえば、さきほどの厨房機器会社では、ただ作業内容を紹介するのではなく、「お客様とのやり取り」や「現場でのエピソード」を交えてコンテンツを制作しました。
あるブログ記事の構成は以下のようなものでした。
- 依頼を受けたのは、開店5周年を迎える人気ラーメン店
- 換気扇から異音がしており、営業中も煙がたまりがち
- 現場調査→深夜作業→翌日、店主の「違う店かと思った」のひと言
- 最後に、同じような症状が出ている店主に向けたアドバイス
こうした“物語型の発信”は、単なるサービス紹介では得られない共感と信頼を引き出します。
さらに効果的なのは、以下のポイントを押さえることです。
- 顔が見える発信(スタッフ紹介や想い)
- 失敗談や試行錯誤も含めて書く
- 顧客からの声や反応をリアルに載せる
✅ コンテンツとは、信頼の蓄積であり、人となりを伝えるツール。
特に小さな企業では、「人」が最大の差別化要因になります。
だからこそ、自社の強みだけでなく、“関わる人の想い”を発信することが、選ばれる理由を生むのです。
差別化とは、他と違うことを言うことではなく、“違いが伝わるように発信し続けること”です。
限定性と専門性でポジションを定め、
ストーリーで共感と信頼をつなぐ。
これが、資金も人材も限られた零細企業が、大手に勝つための王道のマーケティング戦略なのです。
次章では、こうした差別化戦略を実行に移すためのマーケティング体制のつくり方を詳しく解説していきます。
人材不足でも実行できるマーケティング体制のつくり方
「やるべきことはわかった。でも、うちは人数が少なすぎて回せないよ」
そう感じた方も多いのではないでしょうか。
実際、マーケティングは戦略を立てるだけでなく、実行・運用の仕組みがなければ成果は出ません。
しかし逆に言えば、仕組みさえ整えば、少人数でもしっかり動かせるのです。
ここでは、これまで私が支援してきた零細企業の現場で、実際に機能している「少人数でも回るマーケティング体制づくり」の考え方と実行法を紹介します。
業務の優先順位と外注・ツール活用のバランス
まず重要なのは、「やることを減らす」ことです。
リソースが少ない企業は、「やらないことを決める」ことが最初の戦略です。
以下は、マーケティング実行時に見直すべきタスクの整理例です。
| タスク | 自社でやるべき? | 外注すべき? | ツールで代替可能? |
|---|---|---|---|
| ブログ記事の執筆 | △(ネタ出しだけ社内) | ◎(ライター外注) | 〇(AI補助ツール) |
| SNS投稿 | 〇(現場のリアルを共有) | △(一部外注も可) | ◎(予約投稿ツール) |
| メール配信 | ◎(顧客理解が前提) | △(テンプレ作成のみ外注) | ◎(MAツール) |
| サイト改善 | △(内容は社内) | ◎(実装は外注) | △(CMSで更新) |
✅ 「手間がかかるが成果に直結しない業務」から手放すのが鉄則。
ツールも積極的に活用しましょう。たとえば…
- NotionやTrelloでタスク管理(誰が何をいつまでに)
- CanvaでバナーやSNS画像の簡易作成
- WordPress+プラグインでSEO設定や予約投稿の自動化
最初から完璧を目指すのではなく、まず“仕組み化”できる部分から着手することが、安定した実行体制の第一歩です。
役割分担と少数精鋭チームの動かし方
少人数だからこそ、「誰が何をやるか」を明確にしないと回りません。
ありがちなのが、全員がマーケティングに関わっているようで、誰も責任を持っていない状態です。
以前、私が支援した従業員5名の製造業では、下記のような“実行チーム”をつくりました。
- 社長:戦略設計と最終判断
- 営業担当:顧客の声・質問を収集して記事ネタを提供
- 事務担当:SNS投稿の管理と簡易レポートの集計
- 外注ライター:コンテンツ制作
- Web業者:月1回のアクセス分析とサイト改善
これにより、マーケティング活動が社内に定着し、半年後には月5本のブログ更新、SNSフォロワーが3倍、問い合わせ件数は2.2倍に増加しました。
重要なのは、以下のような“シンプルな役割分担”を明文化することです。
- 意思決定者:誰がゴールを決めるか
- 情報収集者:顧客と接点がある人
- コンテンツ提供者:現場のネタを出せる人
- 発信担当者:誰が投稿・更新を行うか
- サポート:外注やツールで補う部分
✅ 人数の少なさは、“役割の重なり”ではなく“責任の曖昧さ”で回らなくなる。
少数精鋭で動かすには、「任せきる」部分と「全員で共有すべきこと」を明確に分けることが重要です。
人材不足という課題は、「仕組み」と「分担」で乗り越えられます。
そしてその仕組みは、特別なノウハウがなくても、日々の仕事の中にある情報や動きからつくり出すことができるのです。
次の章では、ここまで紹介した戦略や体制づくりに関するよくある疑問やつまずきやすいポイントについて、Q&A形式で整理していきます。
よくある疑問と課題に答えるQ&A
これまで、零細企業がマーケティングで成果を出すための戦略や実行体制についてお伝えしてきました。
しかし実際に現場で動こうとすると、「これって本当に必要?」「うちにも当てはまるの?」といった疑問が出てくるものです。
ここでは、私・柳井が日々のコンサル現場でよく受ける質問の中から、特に多い2つを取り上げて、明快かつ実務的な視点でお答えします。
SNSはやるべき?やらなくていい?
この質問、よく聞かれます。
結論から言うと、「目的が明確ならやるべき、なんとならやるくらいならやらなくていい」です。
SNSはあくまで“手段”です。
ブランディング、ファンづくり、採用、顧客との接点づくりなどにおいては非常に有効ですが、「SNSをやれば売上が上がる」とは限りません。
以下に、零細企業でSNSを活用すべきパターンを整理しました。
| 状況 | SNS活用の是非 | 目的 |
|---|---|---|
| 顧客がSNSをよく使っている | ◎やるべき | 認知・接点づくり |
| リピート客との関係を深めたい | ◎やるべき | 継続利用・紹介促進 |
| 情報発信のネタが多い業種(飲食・美容など) | ◎やるべき | 日常発信で親近感獲得 |
| BtoBで決裁者に届きづらい | △慎重に判断 | 信頼の補完として活用 |
| 社内に更新できる人材がいない | △やらなくてもいい | 無理に始めない |
実際、以前私が支援した町工場(BtoB)では、SNS運用を一度やめて、ブログと展示会フォローに集中した結果、問い合わせが安定的に増加しました。
✅ やるかどうかの判断基準は「目的に合っているか」「継続できるか」の2つだけ。
ムダな運用で疲弊するくらいなら、今すぐ手放して問題ありません。
BtoBとBtoCで戦略はどう変わる?
こちらも頻出質問ですが、ポイントは「意思決定のプロセスの違い」です。
BtoB(法人向け)とBtoC(個人向け)では、購買に至るまでの心理や情報の求め方が異なります。
| 比較項目 | BtoB | BtoC |
|---|---|---|
| 購買の特徴 | 複数人での検討・合理的判断 | 感情やタイミングが影響 |
| 検討期間 | 数週間~数ヶ月 | 即決~数日 |
| 情報ニーズ | 導入効果、実績、仕様、費用対効果 | 使用感、雰囲気、ベネフィット |
| 信頼のつくり方 | 実績・専門性・継続発信 | 共感・ストーリー・ビジュアル |
例えば、BtoBではホワイトペーパー、技術ブログ、セミナー資料などが有効ですし、
BtoCではSNS投稿、レビュー、動画、写真などが効果的です。
✅ 「誰に届けるか」が変われば、「何を、どう伝えるか」も変わる。
ですから、自社がBtoBかBtoCかだけでなく、「その中でも誰に向けてか」を明確にすることで、戦略はより洗練されます。
疑問をひとつひとつ解消していくことで、マーケティングは“やるべきこと”が見えてくるものです。
人材不足や少人数という条件をマイナスに捉えるのではなく、戦略的に活かす視点を持つことこそが、現代の零細企業にとっての最大の武器になります。

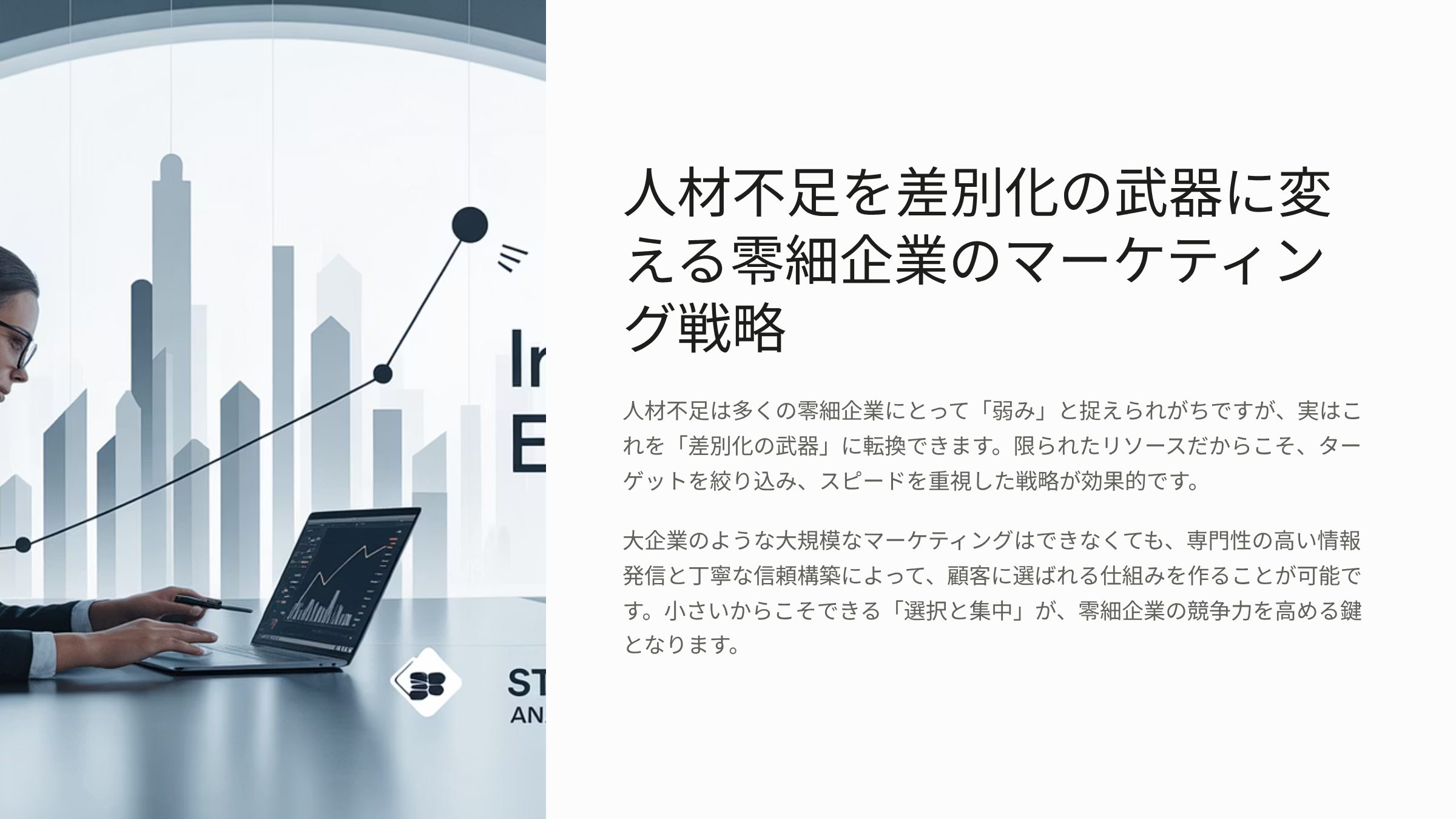









コメント