人手不足で倒産寸前だった老舗企業が、アウトソーシング導入で見事に復活。その軌跡から、現場の再生に必要な本質が見えてきます。目次を見て必要なところから読んでみてください。
人手不足倒産の危機に直面した老舗企業の現実(検索意図を網羅)
なぜ人手不足で倒産寸前に追い込まれたのか
「まさか自分の代で店を畳むことになるなんて――」
そう話すのは、創業60年を超える町工場の3代目社長・木下さん(仮名)。先代から受け継いだ精密部品加工の技術と信用を守り抜いてきたが、数年前から徐々に異変が起きていた。求人を出してもまったく応募が来ない。退職者が出ても補充ができず、現場は慢性的な人手不足に。
特に致命的だったのは、技術者の高齢化が一気に進んだことだ。現場を支えていた職人の一人が体調を崩して退職したのをきっかけに、納期遅延が続出。取引先からの信頼も揺らぎ、売上は前年から30%減少した。
「社員には無理をさせていたし、自分自身も寝る暇もなかった。でも、どうすれば良かったのか分からなかったんです。」
経営に真面目な人ほど、自力で何とかしようと抱え込みがちだ。だが、人手不足は“経営努力”だけではどうにもならない領域に入ってきている。
業界全体に広がる深刻な人手不足問題
木下さんの会社だけが特別ではない。帝国データバンクの調査によると、2024年の「人手不足倒産」は前年比19.5%増加し、過去最多を記録した。特に影響が大きいのは以下の業種だ。
- 製造業(とくに機械加工・食品加工など技能系)
- 建設業(熟練工不足が顕著)
- 運輸業(ドライバー確保が難しい)
- 小売・サービス業(シフト制で人が集まりにくい)
この背景には、以下の構造的な要因がある。
- 人口減少による若手労働力の不足
- 都市部への人材集中による地方の空洞化
- 技能継承が進まないことによる高齢化リスク
また、求人広告や採用活動にコストをかけても成果が出ない時代に突入している。求人を出す→応募が来ない→現場が疲弊→退職者が出る…という負のスパイラルに陥ってしまうのだ。
ここで重要なのは、「人が足りない」という事実だけでなく、「どうして人が集まらないのか」「なぜ今までのやり方では通用しなくなったのか」を冷静に見つめ直すこと。
実は私自身(柳井弘幸)も、以前に支援したある地方企業で同じ課題に直面しました。社員数10名の建築資材会社でしたが、社員の平均年齢は58歳、営業担当はたったの1名。年間の売上は減少の一途でした。
しかしこの会社は、業務の見直しとアウトソーシングを組み合わせたことでV字回復を実現したのです。次章では、その「転機」について詳しくお話しします。読者のあなたにとっても、まだ可能性はあると信じています。
あなた:
##アウトソーシングという光明に出会うまで(H2単位で完結) ###経営者が直面した「このままでは終わる」という恐怖 ###外部パートナーとの出会いが転機に
プロマケSEO記事作成 の発言:
アウトソーシングという光明に出会うまで(H2単位で完結)
経営者が直面した「このままでは終わる」という恐怖
「正直、もう潮時かと思ったんです。」
そう話してくれたのは、前章に登場した木下社長。売上の減少と人手不足が続く中で、追い打ちをかけるように長年取引してきた大手顧客からの契約打ち切りが通告された。原因は、納期の遅れと品質低下だった。
当然ながら、現場は混乱した。残った社員にも限界が近づいていた。社長自身も現場作業に入り、土日も休まず対応していたが、「自分が倒れたら終わりだ」と初めて現実を突きつけられたという。
その頃には、すでに採用活動に数百万円を投じていたが、応募ゼロが続いていた。ハローワークにも、求人広告にも、何の反応もない。
「求人出せば人が来る時代じゃないんだな、とやっと気づいたんです。でも、じゃあどうすればいいかが分からなかった。」
私(柳井)も、現場を歩いて感じました。問題は“人が足りないこと”そのものではなく、“人手がないと回らない仕組みのまま”放置していたことにあったのです。
人を増やせないなら、人に頼らない仕組みを作る。その視点が、転機につながっていきました。
外部パートナーとの出会いが転機に
転機は、地元商工会議所でのセミナーがきっかけでした。
テーマは「中小企業の業務改善とアウトソーシング活用」。木下社長は最初、懐疑的でした。
「アウトソーシングって、大企業がやるものでしょう?」
そう思っていたのです。しかし、セミナーで紹介された事例は、従業員10名未満の企業でも、業務の一部を外部に委託することで、経営が安定したという内容でした。
具体的には、以下のような業務を委託していました。
- 総務・人事の事務処理(給与計算・勤怠管理)
- 経理(記帳・請求・月次レポート)
- 営業支援(テレアポ・資料作成)
- 製造工程の一部(組立・検査・発送)
社長の心が動いたのは、「すべての業務を手放す必要はない」というアドバイスでした。核心は、「社内でなければならない仕事」と「社外に出しても支障がない仕事」を分けること。
この考え方に触れたことで、木下社長は少しずつ目の前の霧が晴れていく感覚を持ちました。
後日、そのセミナーで紹介された中小企業支援の専門会社と面談し、業務フローの見直しを開始。まずはバックオフィス業務から外注することに決めたのです。
不安はあった。コストも気になった。しかし、試算してみると、新たに1名採用するよりも安く、かつ即戦力のサポートが得られると分かった瞬間、社長はようやく腹を決めました。
「人を増やす以外にも、道があるんだと知れたことが一番大きかったです。」
この決断が、後に会社の復活を支える大きな土台となっていきます。次章では、どのように業務を見直し、外注を組み込んでいったのか、実際のプロセスを追っていきましょう。読者のあなた自身の職場にも、必ず応用できるヒントがあるはずです。
復活の鍵は業務の見直しとアウトソーシング戦略(H2単位で完結)
業務棚卸で見えた非効率の数々
アウトソーシングを導入するには、いきなり「これを外注しよう」と動くのではなく、まず社内業務の棚卸し=見える化が欠かせません。
木下社長も、支援会社のアドバイスを受けながら、全社員の1日の業務内容を30分単位で記録し、それをもとに次のようなリストを作成しました。
- 作業時間
- 業務の目的
- 担当者
- 作業場所
- 社内 or 社外のどちらでもできるか
その結果、驚くような事実が次々と明らかになりました。
- 経理担当者の3割の時間が紙の伝票整理
- 営業社員が訪問資料の作成に1日2時間もかけている
- 社長自身が勤怠管理をExcelで集計していた
つまり、「人手が足りない」と思っていたのは、本来やるべきでない仕事を、限られた人材が抱えていたからだったのです。
実際に業務をカテゴリ別に整理すると、以下のように分類されました。
| 業務カテゴリ | 作業内容(例) | 対応方法 |
|---|---|---|
| コア業務 | 技術加工、製品検査 | 社内対応 |
| ノンコア業務 | 経理処理、勤怠管理、資料作成 | 外注検討 |
| 雑務・非生産 | 来客応対、掃除、伝票整理 | 外注または簡素化 |
✅ 棚卸しのポイントは、「この仕事は本当に社内でなければならないか?」を一つずつ問い直すこと。
このプロセスを通じて、木下社長は「人手不足の本質は“仕事のムダ使い”だった」と気づくことになります。
どの業務を外注すべきか?判断の軸とは
では、見えてきた業務の中からどれをアウトソーシングすべきか? その判断には明確な軸があります。支援会社との話し合いで決まった基準は、以下の5つです。
- 専門知識が必要だが社内にノウハウがない業務
→ 例:経理、法務、ITサポート - 手間がかかるが付加価値を生まない業務
→ 例:データ入力、資料作成、備品管理 - 繁閑の差が大きく、常時雇用が難しい業務
→ 例:季節変動がある製造工程 - 属人化が進み、他者に引き継げない業務
→ 例:社長だけがやっている事務処理 - 外注しても機密性や品質が維持できる業務
→ 例:バックオフィス系のルーチン作業
この基準に基づき、まず最初に委託したのは「給与計算」「帳簿記帳」「営業資料の作成支援」の3つでした。これにより、月に40時間以上の工数を削減できたのです。
外注先の選定も、「価格」だけでなく、以下のような観点で慎重に進めました。
- 実績や対応業種の近さ
- セキュリティ体制やサポート体制
- 契約の柔軟性(期間・トライアル対応)
✅ アウトソーシングは、丸投げではなく“協業”として捉えるべきです。
木下社長も、定期的にオンラインで報告を受けることで、「外注=ブラックボックス」という不安を払拭できたと振り返ります。
こうして、少しずつ社内のリソースを「本来やるべき仕事」に集中できる体制が整っていきました。そしてこの変化は、やがて業績と社員のモチベーションにも明確な結果をもたらすことになります。次章では、実際にどのような成果が生まれたのかを見ていきましょう。
アウトソーシング導入後の変化と成果(比較・事例・Q&A等)
人手不足が解消し、社員の笑顔が戻った
「最近、工場が明るくなった気がする。」
ある日、取引先の担当者がつぶやいたその言葉に、木下社長はハッとしました。以前はピリピリした空気が漂っていた現場。社員は疲弊し、誰もが自分の業務に追われ、余裕をなくしていた。だが、アウトソーシングの導入から3か月、現場の雰囲気は明らかに変わっていたのです。
具体的な変化は、以下の通りです。
- ✅ 毎日の残業が平均1.5時間から30分以下に
- ✅ 資料作成や事務作業が社員の手を離れ、本来業務に集中できるように
- ✅ 若手社員が「ここで働き続けたい」と話すように
社員の中には、「もっと改善できることがある」と自発的に業務フローの見直しを提案するメンバーも現れました。アウトソーシングは単なる“外注”ではなく、社内に“余白”と“自律性”を取り戻す手段でもあったのです。
木下社長も、久しぶりに土曜日に家族と出かけたと言います。仕事と向き合う気持ちにも変化が生まれ、「もうダメだ」と思っていた日々が、うそのように遠く感じられるようになったと。
経営指標で見る復活の足跡(売上・利益・定着率)
感情面の変化だけではありません。数字にも明確な改善の兆しが表れました。
アウトソーシング導入から半年後、以下のような成果が記録されています。
| 指標項目 | 導入前(前年比) | 導入後6か月後(前年比) |
|---|---|---|
| 売上高 | -18% | +9% |
| 営業利益 | -25% | +6% |
| 離職率 | 22% | 5% |
| 平均残業時間(月) | 45時間 | 18時間 |
| 採用コスト(年) | 約180万円 | 約30万円 |
✅ とくに注目すべきは「離職率」と「営業利益」の改善です。
業務の属人化が解消されたことで、仕事の引き継ぎやチーム内のサポート体制も整い、社員の安心感が格段に増しました。
また、社長自身が新規開拓営業に時間を割けるようになった結果、2社の新規取引が実現し、それが売上増加の原動力にもなっています。
このように、アウトソーシングはコスト削減の手段ではなく、“経営資源の再配分”として捉えることが大切です。限られた人材・時間・予算を、最も価値を生む仕事に集中させる――この本質に気づいた企業こそ、次の時代を生き抜く力を持てるのだと思います。
最後に木下社長が言っていた言葉を紹介して、締めくくりとしましょう。
「アウトソーシングは、会社の“外”に助けを求めたことじゃない。もう一度、自分たちの“中”にある強みに気づくためのきっかけだったんです。」
次章では、同じ悩みを抱える企業が、どんな視点でアウトソーシングを導入すればよいか。失敗しないポイントを整理してお伝えします。あなたの会社にも、必ず応用できるヒントがあるはずです。
同じ悩みを抱える企業へのヒント(比較・事例・Q&A等)
アウトソーシング成功のための3つのポイント
木下社長のように、アウトソーシングを通じて経営再建に成功する企業がある一方で、「外注したのに逆に手間が増えた」「コストばかりかかって効果がなかった」と感じる企業も少なくありません。
その違いは何か?
私(柳井弘幸)がこれまで中小企業の支援を通じて感じてきたのは、アウトソーシングは「やり方」より「考え方」で差が出るということです。単なる作業の外注ではなく、「経営戦略の一部」として位置づけるべき取り組みなのです。
成功企業に共通する、3つのポイントを整理しましょう。
① 目的を明確にする(手放したいのは時間?人件費?専門性?)
最初にやるべきは、「なぜ外注するのか」を明確にすることです。
たとえば…
- 社内工数を減らしたい → 業務整理が必要
- 専門スキルを補いたい → 高度な業務委託先を探す
- 離職リスクを下げたい → 属人化解消が優先
目的がブレると、外注範囲もずれます。結果、失敗するリスクが高まります。
② 小さく始めて、成果を確認する
いきなり全業務を外注するのはリスクが大きすぎます。
最初は1業務、1部門、1ヶ月など、「スモールスタート」で試すことが鉄則です。
たとえば木下社長の会社では、以下の順で進めました。
- 給与計算(ルーチン・機密性あり・判断しやすい)
- 経理(記帳・仕訳のみ)
- 資料作成(営業サポート)
段階的に進めることで、社内の理解と納得感も高まりやすくなります。
③ 社内と社外を“つなぐ役割”を必ずつくる
「外に出したら、丸投げでOK」ではありません。
むしろ、外部とのやりとりを管理する“窓口役”の存在が成果を大きく左右します。
その役割を果たすのは、必ずしも管理職でなくてもかまいません。
重要なのは、以下のような対応を担うことです。
- 外注先との連絡・進捗管理
- フィードバックの整理
- 社内メンバーとの橋渡し
✅ 外注=外の人という認識をやめ、外注=“共に働くチーム”という意識転換が不可欠です。
よくある誤解と注意点とは?
最後に、私が現場でよく耳にする「アウトソーシングの誤解」と、その注意点を紹介します。
誤解①「外注はコストが高い。自分でやったほうが安い」
→ 確かに“単価”だけを見ると高く感じることがあります。
しかし、社員1人を雇う固定費(月30万円前後)と比べ、外注は変動費で管理できるのが大きな利点。
必要な時に、必要な量だけ頼める柔軟性を考慮すると、むしろ合理的です。
誤解②「外注すると品質が落ちる」
→ これは選び方と伝え方の問題です。
適切なパートナー選定と、期待値・仕様のすり合わせができていれば、社内より高品質な結果が出るケースも多いです。
誤解③「うちの会社は小さいから、外注なんてムリ」
→ むしろ、リソースが限られている小さな会社ほど、外部の力を借りることで成長のチャンスが広がるものです。
最近では、月数万円から対応できる小規模向けサービスも増えています。
注意点:アウトソーシングは「戦略的判断」
最後に、忘れてはならないのは、アウトソーシングは一時しのぎではなく、会社の未来を左右する“経営判断”であるということです。
- どこに集中するか
- 何を外に任せるか
- どう信頼関係を築くか
この3つを見極めることで、人手不足に強い“自走する組織”への一歩が踏み出せるのです。
次の時代も生き抜ける企業になるために、今こそ、働き方と経営の「前提」を見直すタイミングかもしれません。
あなたの会社の中にも、きっと変化の種が眠っているはずです。



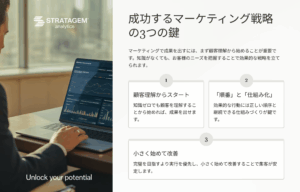
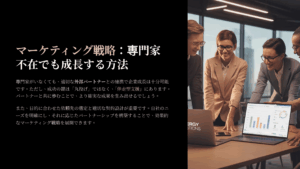
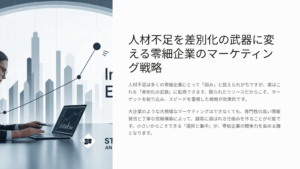
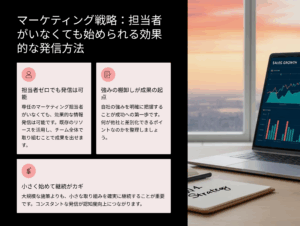
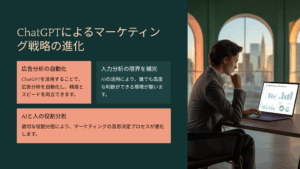
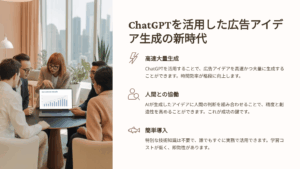


コメント