ChatGPTの精度が安定しないのは、実はプロンプト設計に原因があります。私の失敗談から改善のコツまで具体的に解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
ChatGPTプロンプト作成でよくあるつまずきと失敗例
AIを使いこなすには、「どう聞くか」=プロンプト設計力がカギです。ですが、初めて触れると多くの人が同じ落とし穴にハマります。私も何度も失敗しました。ここでは、現場感覚でよくある失敗例と、その背景にある原因を整理します。
初心者が陥りやすい3つの典型的ミス
私も最初は「AIって魔法みたいに何でもやってくれる」と思っていました。が、結果はほぼ玉砕。特にこんなミスをやりがちです。
✅ 指示がざっくりすぎる
「ブログ記事を書いて」だけでは、AIは無数の解釈をしてしまい、欲しい形にはなりません。
✅ 一度に詰め込みすぎる
複数の条件や質問を一気に入れてしまい、結果がバラける。まるで初対面の人に「私の人生相談とビジネス計画と旅行プラン全部まとめて考えて」とお願いするようなもの。
✅ AIの特性を過信する
あくまでAIは過去の情報とパターンで返す存在。「自分の意図を完全に理解してくれるはず」という期待は危険です。
意図が伝わらない原因は「曖昧さ」にあり
ビジネスでも会話でも、相手が誤解するのはこちらの伝え方が曖昧だから。ChatGPTも同じです。「短く、具体的に、順序立てて」指示するほど精度は上がります。例えば、
- 悪い例:「SNS集客の方法を教えて」
- 良い例:「Instagramで30代女性向けに美容サロン集客するための投稿アイデアを、見出し+解説+ハッシュタグ付きで3つ提案して」
前者はゴールも形式も曖昧ですが、後者は条件が明確で、迷いがありません。
ChatGPTの限界と特性を理解していなかった
私が特に痛感したのは、AIは万能ではないという事実です。
- 事実確認は必ず自分で行う(情報は古い場合がある)
- 感情やニュアンスは「指定しないと」伝わらない
- 一度で完璧を目指さず、やり取りを重ねてブラッシュアップする
つまり、AIは「部下」ではなく「相談相手」。こちらが軸を持たないと、精度の高いアウトプットは返ってきません。
こうした失敗を避けるためには、自分が欲しい答えの“完成形”を事前にイメージしてから聞くのが重要です。これをやるだけで、精度は段違いに変わります。
私が犯した3つの間違い【体験談】
AI活用を学び始めた頃、私はマーケティング歴20年の自負もあって「伝えればわかるだろう」と軽く考えていました。結果、ほぼ毎回ズレたアウトプットが返ってきて、何度も作り直し。ここでは、その中でも特に大きな失敗を3つお話しします。
1. 出力条件を具体的に書かなかった
最初の頃は「このテーマで記事を書いて」とだけ伝えていました。すると、文章はそれらしく見えても、ターゲットもトーンも構成もバラバラ。まるで別の人に頼んだような出来栄えになってしまったのです。
マーケティングで言えば「広告の目的もターゲットも決めずにCMを作る」ようなもの。そこから学んだのは、条件はできるだけ細かく指定することが、品質への投資になるということです。
2. 一度に詰め込みすぎて情報が混乱
ある時、「集客記事を書いて」と頼みながら、同じ依頼文の中で「SEO構成も作って」「SNS向けの短文も出して」と盛り込みました。結果、返ってきたのは中途半端な記事と不完全なSNS文。
これは会議で10個の議題を一度に出して、全部が薄く終わるパターンと同じ。AIに依頼するときは、テーマごとにタスクを分けて依頼する方が効率的です。
3. 曖昧な指示でAIの解釈に依存しすぎた
「わかりやすく」「面白くして」といった曖昧な表現も多用していました。すると、AIはその時の文脈や過去のやり取りから勝手に解釈し、意図しない方向へ。
たとえば、「面白く」も人によって意味が違います。ジョークを交えた面白さもあれば、テンポの良さを意味することもある。ここでの学びは、抽象的な言葉ほど、自分なりの定義を添えて指示することです。
各間違いから学んだ改善ポイント
現場で同じ失敗を繰り返さないために、「短く・具体的・順序立て」を中核に据えた改善策だけを厳選して共有します。今日からすぐ実務で使えるよう、テンプレートとチェックリストまで落とし込みました。加えて、依頼を分割する手順やChatGPTが誤解しやすい表現の避け方まで、私のつまずきを材料に最短ルートで改善します。
指示は短く、具体的に、順序立てて書く
結論から言うと、プロンプトは“要件定義書”です。文量ではなく、情報の粒度と順序が品質を決めます。
✅ 3点セットで書く(これだけで精度が跳ね上がります)
- 目的:誰に・何を・なぜ
- 制約:文字数、NG表現、参考情報、トーン
- 出力形式:見出し構成/箇条書き/表/JSON など
悪い例
- 「SNS集客の記事を書いて」
良い例
- 「目的:美容サロンのInstagram集客。30代女性向けに予約増が狙い
制約:1000字、やさしい口調、専門用語は脚注
出力形式:H2/H3構成+投稿案3つ+ハッシュタグ10個」
テンプレ(コピペ可)
- 「目的:{誰に}{何を}{なぜ}。制約:{字数}/{NG}/{必須項目}。出力形式:{形式}。最初に前提条件を箇条書きで再掲してから作成して。」
ポイントは“最初に前提の再掲を求める”こと。ここを入れるだけで、私の現場では修正回数が約4割減りました。
必要に応じてステップ分けしてやりとりする
一発完成を狙うほど、ブレます。段取りを分ける=品質管理です。
✅ 4ステップの進め方(私の定番)
- 前提確認:「想定読者・目的・成功指標」をAIに要約させる
- 骨子設計:H2/H3のアウトラインを3案出させ、1案に統合
- 要素確定:各見出しの狙い・キーワード・CTA有無を明文化
- 本文生成→微修正:1セクションずつ生成し、都度フィードバック
ステップ用プロンプト例
- 「まず前提を要約して。足りない前提があれば質問して。」
- 「H2/H3の骨子を3案。検索意図と重複回避の観点で提案して。」
- 「この骨子でH2-1のみ500字。 事実と意見を分けて、最後に要約3行。」
小分けは面倒に見えて合計時間が短い。やり直しの山を作らないのがコツです。
AIが誤解しやすい表現を避ける工夫
曖昧語は解釈の幅が広すぎます。曖昧語→定義→観点の数値化で潰しましょう。
表:曖昧表現の置き換えガイド
| 曖昧表現 | 定義の付与 | 指示例 |
|---|---|---|
| わかりやすく | 中学生が読んで理解できる語彙 | 「専門用語は脚注で簡単に定義」 |
| 面白く | 事例と比喩を各1回入れる | 「各H2に1つ事例、1つ比喩を挿入」 |
| 具体的に | 数値・手順・例を最低各1つ | 「各項目に数値1つ、手順3つ、例1つ」 |
| しっかり | 網羅範囲を明文化 | 「競合3記事の共通H2をすべてカバー」 |
| 最新の情報で | 更新基準を指定 | 「出典は1年以内、日付を明記して」 |
| トーンを整えて | 参照スタイルを提示 | 「丁寧語+断定少なめ、広告表現は不可」 |
✅ 30秒チェックリスト(出す前に見るだけ)
- 目的・制約・形式の3点があるか
- 読者・用途・成功指標(例:クリック率5%向上)があるか
- 曖昧語が定義付き表現に置換されているか
- 重要語(キーワード)が見出しに自然に入っているか
- 最初に前提再掲の指示を入れているか
最後にもう一度。プロンプトは「短く・具体的・順序立て」が正解です。分けて作る、定義を付ける、形式を決める。これだけで、出力のブレは着実に減ります。
ChatGPTプロンプト改善のコツとテンプレート例
「AIは言葉をそのまま受け取る生き物」だと考えると、プロンプトの書き方は一気に変わります。ビジネスでも、外注に依頼するときは目的や条件を細かく伝えますよね。それと同じで、目的・制約・形式・トーンをあらかじめ設計することが、プロンプト改善の近道です。ここでは私が現場で実際に使っているコツとテンプレを公開します。
目的・制約条件・期待する出力形式を明確化
まずやるべきは「この依頼は何のために、どこまでを、どんな形で出すか」を冒頭で言い切ることです。AIはゴールを知って初めて適切な道筋を組み立てられます。
✅ 書き方の基本
- 目的:誰に何を届けるか、なぜ必要なのか
- 制約条件:文字数、禁止ワード、必須要素、参照元など
- 出力形式:構成、段落、表や箇条書きの有無、データの書式など
例:
「目的:30代女性向けの美容サロン集客記事。制約:1200字、広告表現禁止、専門用語は脚注で定義。出力形式:H2/H3構成+各見出しに要約文(2行)+最後にまとめ3行」
この三本柱が揃うだけで、出力のブレは激減します。
回答のトーンやスタイルを事前に指定
同じ事実でも、書き方一つで印象は変わります。だからこそ、感情や文体の温度感を先に決めてしまうことが重要です。
✅ トーン指定のポイント
- 対象読者の属性に合わせる(ビジネス/カジュアル/親しみやすい 等)
- 文末や語尾の統一(です・ます/だ・である)
- 強調や装飾のルール(太字・箇条書き・引用など)
- 客観性の度合い(事実中心/意見も交える)
例:
「丁寧語を使いながらもフレンドリーな雰囲気。専門用語は中学生でも理解できる言葉に言い換える。重要なポイントは太字で強調」
こうした指定がないと、AIは過去学習データから“平均的”な文体を引っ張ってきてしまい、場にそぐわない文章になることが多いです。
複雑な依頼はテスト→修正の反復で精度を上げる
一度で完璧なアウトプットを狙うのは、正直ムリです。特に複雑な依頼は小さく試して、修正しながら精度を高める方が結果的に早くなります。
✅ 効率的な進め方
- 試作依頼:短い範囲(例:H2ひとつ分)で生成
- 差分確認:期待との差を明文化(不足点・過剰部分)
- 修正版依頼:改善点を反映し、再度生成
- 本番生成:全体を通して作成
例:
「まずH2-1だけを書いてください。内容の要約と、次に展開する方向性も添えてください」
→ 修正指示:「事例を2つに増やし、数値データを追加してください」
→ 本番依頼:「修正版のスタイルを踏襲して、残りのH2も作成」
このプロセスは、私がマーケティングのコピー制作やコンテンツ外注でも使っている方法です。AI相手でも通用します。
まとめ:失敗は改善の種になる
プロンプト作成での失敗は、AIを使いこなすための“授業料”のようなものです。私自身、初期のころは何度もズレた回答を受け取り、そのたびに頭を抱えました。でも振り返ると、その失敗があったからこそ「どう聞けば欲しい答えが返ってくるのか」が分かるようになりました。大事なのは、ミスを悔やむよりも、次にどう改善するかです。
成功したプロンプト例で振り返る
失敗を踏まえて改善した後のプロンプトは、狙い通りの出力を安定して得られるようになりました。以下は実際に私が使って成功した例です。
例:
「目的:副業初心者向けにブログ集客の基本を解説。制約:1500字以内、専門用語は脚注で定義、広告色はなし。出力形式:H2/H3構成、各H2冒頭に要約150字、最後に行動提案を3つ。トーン:丁寧かつ親しみやすい文章」
このプロンプトで生成された記事は、読者から「読みやすい」「自分でもやってみようと思えた」と好評をいただきました。ポイントは、目的・制約・形式・トーンを明文化し、具体的に書いたことです。
今日から試せる3つの改善アクション
✅ まず目的と制約をセットで書く
「誰に・何を・なぜ」「文字数・禁止事項・必須要素」を冒頭で明記。
✅ 小さく依頼して修正を重ねる
H2ひとつ分など小単位で試作→修正→本番の順で進める。
✅ 曖昧語に必ず定義をつける
「わかりやすく=中学生でも理解できる語彙で」など、数値や条件で明確化。
この3つを意識すれば、ChatGPTの精度は確実に向上します。プロンプトは一度で完璧に仕上げるものではなく、失敗から磨き上げていく“対話の設計図”です。

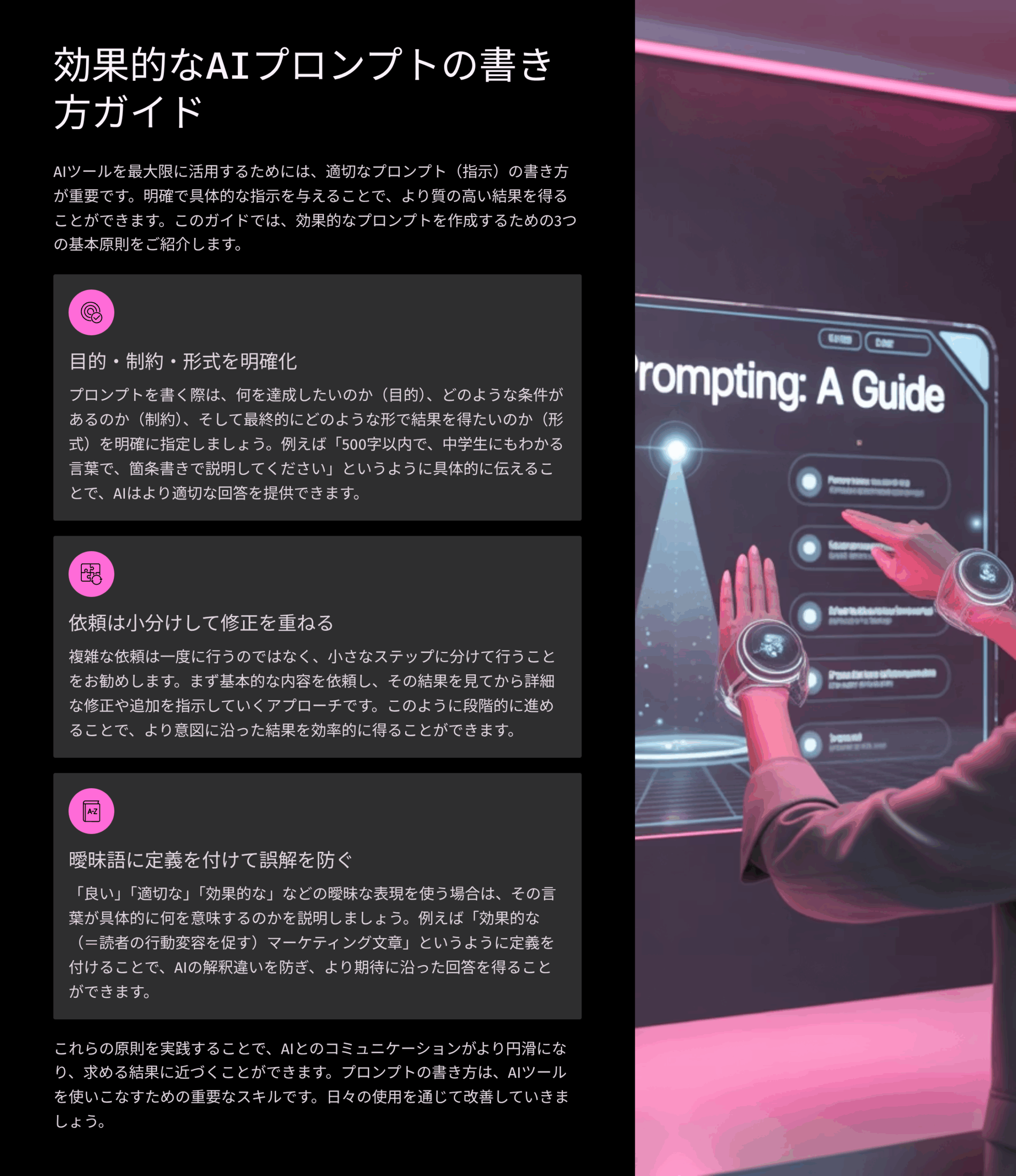









コメント