ChatGPTを使った企画書作成は本当に時間短縮できるのか。実際の比較データと活用法を交えて詳しく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
ChatGPT活用による企画書作成時間の変化【データで比較】
企画書って、作るたびに「もっと早く終わらせたい」と思いませんか。私もかつては何日もかけて練っていましたが、ChatGPTを取り入れてからは状況が一変しました。この章では、活用前後の作業時間を数値で比較し、その効果を客観的に把握していきます。数字は感覚ではなく事実を物語ります。
活用前と活用後の作業時間の記録方法
まず、比べるためには「正しい記録」が欠かせません。私が行ったのは、毎回の企画書作成で開始時間と終了時間をストップウォッチ感覚でメモするだけというシンプルな方法。
✅ 記録項目の例
- 日付
- 作成プロジェクト名
- 開始時刻・終了時刻
- ChatGPTの利用有無
この記録を最低でも5件ずつ取ることで、偶然ではなく傾向が見えるようになります。感覚頼みではなく、データに基づく判断ができるわけです。
記録期間・条件・前提の設定
数字は条件次第でいくらでも変わってしまいます。そこで私が設定したのは、以下の3つのルールです。
- 対象は新規作成の企画書のみ(既存資料の修正は除外)
- 同じレベルの情報量とページ数(平均8〜10ページ)
- 使用するツールや情報源は固定(ChatGPT以外の条件は変えない)
この前提を守ることで、比較の精度がグッと高まります。マーケティングでもA/Bテストの条件統一は鉄則ですが、ここでも同じ考え方が必要です。
実際の時間比較表とその読み解き方
では実際の数値を見てみましょう。これは私が1カ月間で記録した平均値です。
| 状況 | 平均作業時間(分) | 最短(分) | 最長(分) |
|---|---|---|---|
| ChatGPT未活用 | 320 | 280 | 360 |
| ChatGPT活用 | 190 | 150 | 230 |
この結果からわかるのは、平均で約40%の時間短縮が実現できたという事実です。特に効果が大きかったのは、構成案の作成や文章の初稿部分。逆に、最終のブラッシュアップは人間の判断が必要なので時間差はそこまで大きくありませんでした。
データを眺めて一番感じたのは、「時間短縮=質の低下」ではないということ。むしろ、早く仕上がる分だけ、練り込みや調整に時間を使えるようになりました。これは私がP&G時代に学んだ「省けるところは省き、価値の源泉に時間を投資する」という考え方とまったく同じです。
企画書作成におけるChatGPTの具体的な活用ステップ
「ChatGPTって、結局どこで使うのが一番効率的なの?」とよく聞かれます。私の経験上、企画書作成のプロセスを3つのステップに分け、その中で役割を明確にすることが成功のカギです。この章では、私が実務で使っている活用ステップをそのままお伝えします。
構成案の自動生成
最初の壁は「構成をどう組むか」です。白紙から考えると、ここでかなりの時間を消耗します。そこで、まずChatGPTにプロジェクト概要と目的を伝え、大見出しと小見出しの叩き台を出してもらいます。
✅ 実務でのプロンプト例
「〇〇プロジェクトの企画書を作りたい。目的は□□で、対象は△△。ページ構成案を5パターン提案してください」
この時点で7〜8割の骨格が整い、私の場合はここだけで30〜40分の短縮になります。もちろん、そのまま使うのではなく、自分の視点で修正することが大前提です。
背景説明や導入文の作成支援
企画書の冒頭は「読む側の理解と共感を得る」ための大事な部分。とはいえ、背景説明や導入文をゼロから考えるのは意外と時間がかかります。
ここでは、ChatGPTに背景となる業界情報や統計データをまとめてもらい、文章化までお願いしています。たとえば、「日本国内の〇〇市場の最新動向を300文字で要約し、課題を明確にしてください」と指示すれば、下地が一気にできます。
その後、実際のプロジェクトに合わせて修正・補足することで、精度とスピードの両立が可能になります。私もスターバックス時代、この“背景の説得力”を軽視して痛い目を見たので、今は必ずここに時間を使います。
提案内容の肉付けとブラッシュアップ
構成と背景ができたら、次は中身の提案部分。ここは「骨」から「肉」に変える作業です。私はまず自分で提案の要点を箇条書きにし、それをChatGPTに渡して「説得力のある文章にリライトしてください」と依頼します。
さらに、反対意見や懸念点を想定してもらい、それに対する回答を用意するのも有効です。これにより、提案の説得力が格段に上がります。
最終的なブラッシュアップでは、文章の流れや言葉のトーンを自分のスタイルに合わせて調整。AIの文章は効率的ですが、「あなたらしさ」は必ず人間の手で仕上げるべきだと感じています。
ChatGPT活用で短縮できた時間の要因分析
「時間が短くなった」と言っても、その理由がわからなければ再現できません。私自身、P&G時代から“成果を分解して原因を特定する”ことを徹底してきました。この章では、企画書作成における時短の源泉を3つの視点から明確化します。これを押さえれば、誰でも安定して効率化できます。
情報収集時間の削減
企画書作成の中で、最も見えにくく、しかも時間を食うのが情報収集です。特に市場動向や事例探しはキーワードの切り口次第で迷宮入りします。
ChatGPTを使えば、複数の情報源をまとめた要約を瞬時に提示してくれます。例えば「〇〇業界の最新トレンドを500文字で」と聞くだけで、骨子が整います。
もちろんAIの情報は最新性や正確性のチェックが必要ですが、ゼロから検索して読む時間は大幅に圧縮できます。私の場合、情報収集だけで平均1時間以上短縮できました。
表現・文章構成の効率化
書く段階でも時間短縮の効果は大きいです。特に、構成案から段落展開までを半自動化できるのが強み。
私は提案の要点や箇条書きをAIに渡し、「説得力のある段落に整えてください」と依頼します。すると、接続詞の流れや説得の順序まで整った文章が数秒で出力されます。
これにより、「どこから書き始めるか」という迷いがゼロになります。迷いがなくなると集中力も持続するため、作業全体のテンポが一気に上がります。
修正回数の減少による時短効果
私が意外だったのは、この効果です。AIで初稿を作ると、骨組みがしっかりした状態でスタートできるため、後工程の修正回数が減ります。
以前は「言い回しが曖昧」「流れが不自然」といった微調整に何度も戻っていましたが、今では大きな修正は1回で済むことがほとんどです。
結果として、後半のブラッシュアップに集中でき、全体の完成度も上がります。これはマーケティングでもよくある話で、入口の精度を上げるほど出口の効率も上がるということです。
実際の比較データから見えた効果と限界
ChatGPTを使えば確かに速くなる――ただし、それは数字で裏付けられてこそ説得力があります。私も1か月分の記録を振り返り、どのくらい短縮できたのか、そしてどこに限界があるのかを冷静に分析しました。ここではその結果を共有します。
時間短縮の最大値と平均値
私の記録では、企画書1本あたりの作成時間は以下のような結果になりました。
| 状況 | 平均短縮時間 | 最大短縮時間 | 短縮率(平均) |
|---|---|---|---|
| ChatGPT活用時 | 130分 | 180分 | 約40% |
最大で180分、つまり丸3時間の短縮ができたケースもありました。これは構成・文章・データ収集のすべてをAIに下ごしらえさせた場合です。
一方で、平均値は130分(約40%)程度。短縮幅が一定しないのは、プロジェクトの複雑さや事前準備の量による差が大きいからです。
短縮効果が出にくいケースと理由
すべての企画書で同じように効果が出るわけではありません。私の経験では、以下のような場合は短縮効果が小さくなります。
✅ 短縮が難しいケース
- 企画の方向性が曖昧な場合
→AIに指示を出す前の準備が長くなる - 高度に専門的な内容が多い場合
→AIの出力を大幅に修正する必要がある - ビジュアルや図解が中心の企画書
→文章よりもデザイン作業の比重が高い
要するに、AIに渡せる材料が揃っていない段階では、短縮効果は限定的です。
これは料理と同じで、素材が決まっていれば下ごしらえは一瞬ですが、レシピから考えなければ時間はかかります。
この結果を踏まえると、ChatGPTは「下地ができている案件を一気に加速させる道具」として使うのが最も効率的だと感じています。
企画書作成時間短縮のためのChatGPT活用ポイント
「ChatGPTを使ったけど、そこまで速くならなかった」という声もよく聞きます。多くの場合、それは使い方の精度に原因があります。私が実務で実感しているのは、プロンプト(指示文)の作り方や運用方法を少し工夫するだけで、短縮効果が2倍以上になるということ。この章では、再現性の高い活用ポイントをお伝えします。
プロンプトの工夫で精度を高める方法
AIの出力は、指示の精度でほぼ決まります。
私が必ず意識しているのは、「目的・条件・制約」をセットで伝えることです。
✅ 例:「新規店舗出店の企画書の導入文を300文字で。目的は若年層顧客の獲得。現状課題は競合増加と集客単価の上昇。読み手は経営陣で、専門用語は少なめに」
こうすることで、出力が的確になり、修正回数が減ります。逆に曖昧な指示だと、修正に時間を取られて本末転倒です。
テンプレート化によるさらなる時短
一度うまくいったプロンプトや構成案はテンプレート化しておくのが鉄則です。
私はGoogleドキュメントに「導入文作成用プロンプト」「市場分析プロンプト」「提案書骨子作成プロンプト」などをまとめ、必要なときにコピペして使っています。
こうすると、毎回ゼロから考える必要がなく、着手までの時間がほぼゼロになります。マーケティングでも「勝ちパターンの再利用」が効率化の王道です。
チームでの共有・活用方法
個人で効率化できても、チーム全体で共有しなければ成果は限定的です。
私の会社では、「ChatGPT活用マニュアル」+「成功事例集」を社内で共有し、誰でも同じレベルで使える環境を整えています。
さらに、週1回のミーティングで「AIが役立ったケース」「逆に時間がかかったケース」を共有し、テンプレートやプロンプトを改善。こうした継続的な改善サイクルが、長期的な時短効果につながります。
ChatGPT活用による企画書作成の事例紹介
「本当にそんなに効果があるの?」と半信半疑の方もいると思います。そこで、私が実際に関わった中から短時間で高評価を得たケースとチーム全体で成果を出したプロジェクトの2つを紹介します。机上の理論ではなく、現場での実例です。
短時間で高評価を得た企画書のケース
ある新サービスの立ち上げ案件で、経営陣に提出する企画書の納期がわずか2日後に迫っていました。通常なら徹夜案件ですが、ここでChatGPTをフル活用。
- 1時間以内に構成案を完成(目的、背景、提案内容までAIで骨組み)
- 市場データの要約と文章化をAIに任せ、3時間で初稿完成
- 残りの時間は事例追加やビジュアル作成など、人にしかできない作業に集中
結果、提出した企画書は「短期間なのに説得力がある」と経営陣から高評価。何より、作業時間は通常の半分以下に抑えられました。
部署全体で活用したプロジェクトの成功例
別のケースでは、部署全体でChatGPTを導入。テーマは全国規模の販促キャンペーン企画です。
✅ 実施した工夫
- 各メンバーが自分のパート(構成案、背景説明、提案内容など)をAIで下書き
- プロンプトやテンプレートを共有し、書き方のブレを最小化
- 最後に責任者が全体を統合・調整
結果、企画書作成期間は2週間から5日に短縮。しかも複数案を同時に出せたため、クライアントへの提案幅も広がりました。
この経験から学んだのは、ChatGPTは「個人の時短ツール」から「チームの生産性ブースター」に進化するということです。導入効果は、共有と仕組み化で何倍にも広がります。
ChatGPT活用に関するよくある質問Q&A
ChatGPTの効果を知っても、「実際に使って大丈夫なのか?」という不安は残ります。ここでは、私が研修やコンサルの場でよく聞かれる質問に、実務経験を踏まえてお答えします。
ChatGPTは企画の独自性を損なわないか?
結論から言うと、使い方次第で独自性は守れます。
AIが出すのはあくまで「一般的に妥当な案」や「既存情報の要約」です。これをそのまま採用すれば、当然オリジナリティは薄れます。
私が意識しているのは、AIを“土台作り”の段階だけで使い、核心部分は自分で肉付けすること。
たとえば、構成案や背景説明はAIで時短し、提案のコンセプトや差別化要素は自分の経験・洞察をベースに書く。これならスピードと独自性を両立できます。
言い換えれば、ChatGPTは「0→1」ではなく「1→5」に進めるための加速装置。企画の魂はあなた自身が吹き込むべきです。
セキュリティや情報漏洩のリスクは?
ここは軽視できないポイントです。
ChatGPTは基本的に入力した情報を学習データに使わない設計(※ただし利用環境による)ですが、機密情報や未公開データは絶対に直接入力しないというルールを徹底しています。
実務での安全対策例:
- プロジェクト名や固有名詞は仮称に置き換える
- 数値や社内データは概算や加工した形で入力する
- 機密案件はオフラインで文章化し、AIは参考情報のみに使う
このように、「出せる情報」と「出せない情報」を事前に線引きしておけば、リスクは大きく減らせます。マーケティングも同じで、公開する情報の取捨選択が安全運用の鍵です。

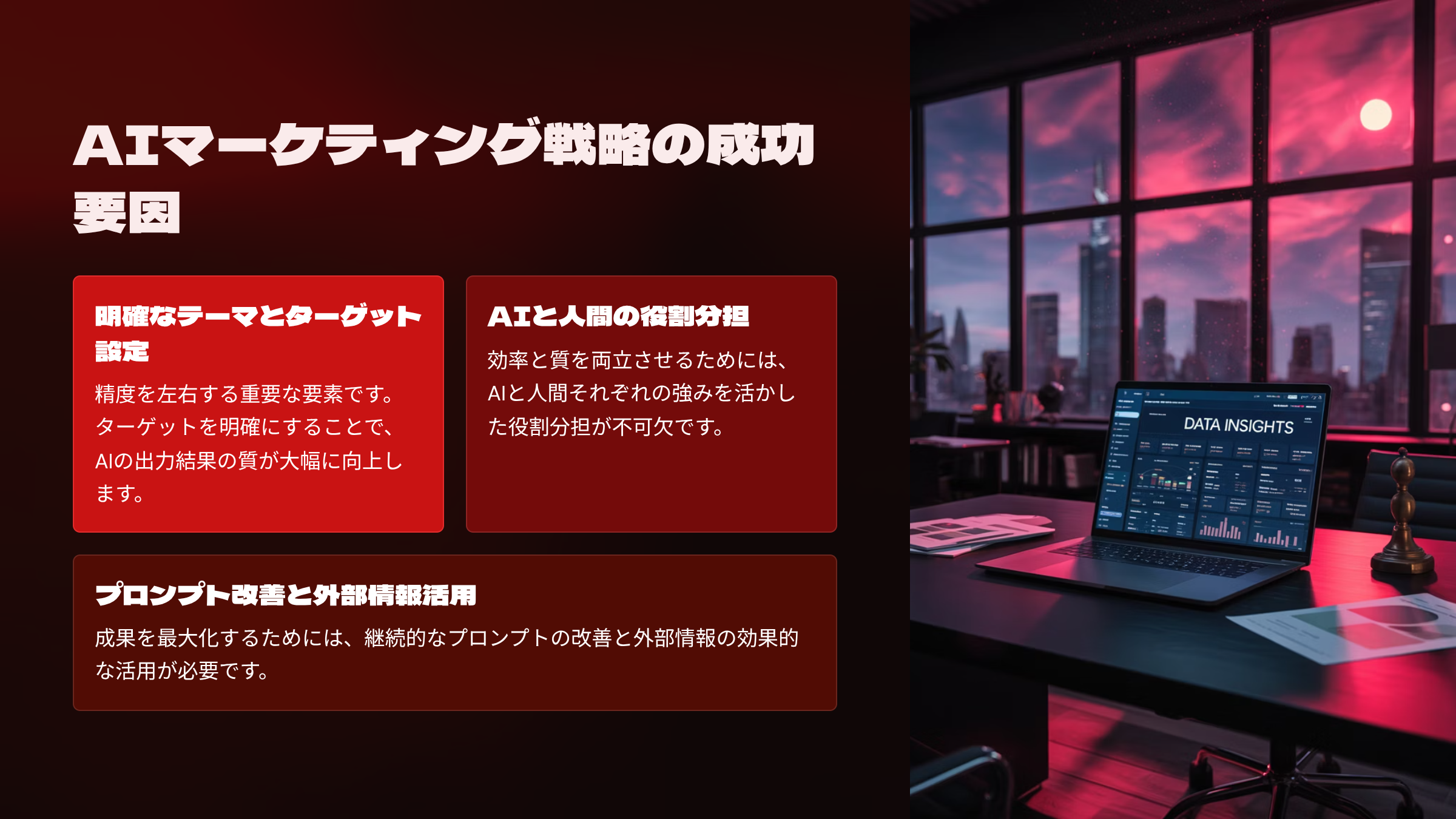









コメント