広告予算を「なんとなく」で配分していませんか?ChatGPTを活用した配分最適化の実例と学びを公開します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
ChatGPTで広告予算を最適化した背景と課題
広告運用におけるよくある予算配分の悩み
「どの媒体に、いくら割くのが正解なのかがわからないんです。」
先日、ある中堅D2C企業のマーケティング責任者から、こんな相談を受けました。広告費は月間300万円、運用媒体はGoogle、Instagram、YouTube。CPCやCPAを見ながら都度配分を調整しているとのことでしたが、成果が安定しない。
もっと予算を集中させたほうがいいのか。
媒体ごとのLTVが違うから単純にCPAだけでは判断できない。
でも全体設計を見直す時間もない。
このような「感覚に頼った広告予算配分」に、現場は思った以上に悩まされています。
かつての私もそうでした。
予算を増やすのは勇気がいる。けれど成果を最大化するには、どこかで戦略的な割り切りが必要。とはいえ、複数媒体での効果測定は時間も手間もかかるし、配分変更には社内稟議もある。
何を基準に判断すればいいのか。
どんなロジックなら、社内で納得してもらえるのか。
そう考えたとき、私はChatGPTを使って「意思決定の筋道」を整理してみようと思ったのです。
従来の手法で感じた限界と非効率
以前は、媒体ごとに月次レポートを眺めながら、次のような作業をしていました。
- スプレッドシートに各媒体のCPC・CPA・CV数を入力
- LTV試算を掛け合わせてROIを計算
- 前月との変化や、季節要因を加味して配分案を作成
これ、一見ロジカルに見えても、実は属人的な要素が多い。
たとえばYouTube広告の成果が先月より良くても、それが「クリエイティブのおかげ」なのか「ターゲティング変更の影響」なのか、すぐには特定できません。
また、判断者の視点や得意領域によって、「インプレッション重視」「コンバージョン重視」などの評価軸がバラつく。
しかも予算調整の意思決定には、上長や他部署の理解も必要で、「なんとなくの説得」では通りにくい。
このあたりで私は、「もっと構造的に考えられないか?」と模索し始めました。
そんなとき目をつけたのが、ChatGPTの情報整理と論点整理のスピードです。
ChatGPTに「配分判断の要素を構造化して」と聞けば、
「目標CPA」「CVの質」「顧客単価」「継続率」「媒体の特性」など、整理された視点が一瞬で出てきます。
さらに、想定ペルソナ別に「どの媒体での反応が良さそうか?」などの仮説も対話形式で深掘りできる。
つまり、広告予算配分のロジックを可視化し、誰が見ても納得できる構成に落とし込める。
この時点で私は、「これは単なる会話AIではない。マーケ戦略の思考補助装置だ」と感じました。
次章では、ChatGPTをどのように広告予算配分に活用したのか、具体的なアプローチをご紹介していきます。ChatGPTを使った広告予算配分のアプローチ
ChatGPTに入力したプロンプトの工夫
ChatGPTを使って広告予算の配分を考えるとき、大事なのは「いかに的確な問いを立てるか」です。
たとえば、私が最初に試したプロンプトは非常にシンプルなものでした。
「広告予算を媒体別に最適に配分する方法を教えてください」
すると、ChatGPTは基本的な配分ルールや効果測定の指標(CPA、ROAS、LTVなど)を挙げてくれましたが、どこか抽象的で「実務感」が薄い印象でした。
そこで次に、具体的な条件を加えたプロンプトに変更しました。
例:プロンプトの改善プロセス
1回目(抽象的な質問)
「広告予算の最適配分を教えてください」
→ 回答:基本的なマーケティング理論の解説(汎用的すぎる)
2回目(条件を追加)
「月間広告予算300万円で、Google広告・Instagram広告・YouTube広告の3媒体を使っています。各媒体のCPA、CV数、LTVが以下の通りです。どのように配分すべきでしょうか?」
→ 回答:具体的なROAS計算+配分の再設計例が提示された
3回目(仮説思考も促す)
「同じ予算内で、ペルソナA(20代女性・スマホから購入)とペルソナB(30代男性・PCから購入)を想定しています。それぞれに効果的な媒体とクリエイティブ戦略を提案してください」
→ 回答:ペルソナごとのメディア適正と、配分の分岐案が出力された
このように、ChatGPTに「背景・制約条件・目的・変数」をセットで与えることで、初めて「実務で使えるレベルの回答」が返ってきます。
つまり、プロンプトは「相談内容」ではなく「設計書」だと考えたほうがいい。
広告配分の意思決定は多くの場合、「一番効果が出るところに全部突っ込む」ではなく、「短期と中長期」「認知と獲得」「顧客層の多様性」などをバランスさせる必要があります。
その整理においてChatGPTは「感覚ではなく構造で考える」ための対話相手になるわけです。
想定ペルソナ別に広告戦略を出力させる方法
予算配分を考える際に、見落とされがちなのが「ペルソナごとの広告接触特性」です。
仮に同じ商品でも、20代と50代では見るメディアも、反応するクリエイティブも違う。
ChatGPTにこの「違い」を整理させることで、媒体別の戦略がより立体的に見えてきます。
私が使っているのは、以下のようなプロンプトです。
例:ペルソナ別戦略出力のプロンプト
「以下の2つのペルソナに対して、広告戦略を設計してください。
- ペルソナA:20代女性、Instagramを毎日使用。コスメやファッションに敏感。衝動買いが多い。
- ペルソナB:30代男性、平日は仕事中心。YouTubeで情報収集するタイプ。購入は慎重。
それぞれに適した媒体、予算配分の比率、訴求軸を提案してください。」
ChatGPTはこれに対して、
- ペルソナAにはInstagram広告中心。訴求軸は「感情・流行性・直感的なビジュアル重視」
- ペルソナBにはYouTube広告中心。訴求軸は「比較・実績・レビュー型クリエイティブ」
というように、ペルソナの行動心理に沿った出力を返してくれます。
さらに、両者をバランスよく獲得するためのクロス戦略(例:リタゲはGoogle広告で共通化)まで提案させると、配分シミュレーションに厚みが出ます。
ここで重要なのは、ChatGPTに「思考の順序」を与えること。
「誰に」「何を」「どこで」「どうやって」伝えるか。この順番でプロンプトを組み立てると、より現場に即した戦略が見えてきます。
結果的に、私はこのアプローチで媒体別の配分を単なる数値ではなく「顧客ストーリーに基づいた判断」として整理できるようになりました。
それにより、社内の他部署との連携もスムーズに。数字の話ではなく、「どの顧客に、どうリーチするか」という会話ができるようになったのです。
次章では、実際にChatGPTの提案を取り入れて配分を見直した結果、どんな変化が起きたのかを具体的にご紹介します。広告予算の配分がどう変わったか
AIが導き出した施策の比較と実行プロセス
ChatGPTに相談したことで、私の広告予算配分の考え方は「現状の最適化」から「戦略的な仮説検証」へとシフトしました。
以前の私は、各媒体のCPAを軸に「数字の良いところに多めに投下」するやり方を取っていました。ですが、ChatGPTにプロンプトを通して課題を整理させてみると、こんな示唆が返ってきたのです。
- Google広告は購入意欲が高い層向けなので、獲得単価は安定するが、獲得数の伸びは頭打ちしやすい
- Instagramは衝動買い層に強く、特定ペルソナに偏っているため、アプローチ次第で大きく化ける可能性がある
- YouTubeは情報収集層への接触点として優れているが、直接CVにはつながりにくい。リタゲ連携が有効
これをもとに、ChatGPTからは次のような配分変更案が提案されました。
Before(従来の配分)
- Google広告:50%
- Instagram広告:30%
- YouTube広告:20%
After(ChatGPTの提案による配分)
- Google広告:40%(リタゲ強化)
- Instagram広告:40%(新規獲得向け)
- YouTube広告:20%(認知と教育用コンテンツ配信)
この提案の背景にあるのは、媒体の「役割」を定義したうえでの配分戦略です。
今までは全媒体で「獲得」だけを狙っていましたが、ChatGPTの出力に従って「認知」「教育」「獲得」「リピート」など顧客フェーズごとの戦略を明確に切り分けました。
さらに、プロンプトを通じて「どのペルソナが、どの媒体で、どんな行動を取りやすいか」まで言語化できたことで、広告チームのメンバーとの連携も格段にスムーズに。
この配分は、あくまで「仮説」として導かれたもの。実際にこれを3ヶ月間テスト実施したところ、明確な成果が見えてきました。
実際の配分変更による効果と数値
配分変更の効果は、獲得数・CPA・LTVの3つの指標で確認しました。
実施期間:3ヶ月(7月〜9月)
月間広告費:300万円(総額は同じ)
| 指標 | Before(旧配分) | After(新配分) | 変化率 |
|---|---|---|---|
| CV(獲得数) | 620件 | 735件 | +18.5% |
| CPA(平均) | 4,838円 | 4,081円 | -15.6% |
| LTV(3ヶ月) | 約12,000円 | 約14,500円 | +20.8% |
特に成果が顕著だったのが、Instagram経由の新規ユーザー。感度の高い層に絞ったクリエイティブ配信を強化したことで、単月のCVRが1.4倍に。
一方、Google広告はあえて配分を減らしながらも、リタゲに特化することでCVRが安定し、結果的にCPAはほぼ変わらず。
YouTubeは獲得こそ少ないものの、後追いのリタゲ経由での間接CVが増えたことが、Googleアナリティクス4のコンバージョン経路から見て取れました。
✅ 重要な気づき:広告媒体ごとに「目的を持たせる」ことが、最終的な効率化につながる
ChatGPTが与えてくれたのは、魔法のような回答ではありません。「仮説を言語化し、施策に落とし込み、検証する枠組み」でした。
結果として、私は広告配分を「感覚」ではなく「構造」で語れるようになり、社内の合意形成も早くなったのです。
次章では、ChatGPTを使う中で見えてきた活用のコツと落とし穴について、率直にお話ししたいと思います。ChatGPT活用で得られた学びと注意点
人間の判断とAIの提案、どこまで任せるか
ChatGPTを広告予算の配分に活用して感じたのは、AIはあくまで「判断の補助輪」であるということです。
私自身、最初の頃はChatGPTの提案に「なるほど、全部その通りにやってみよう」と思って、提案された配分をそのまま実行したことがありました。しかし結果として、意図と異なる層からのCVが増え、LTVが下がったこともあります。
なぜか?
ChatGPTは、論理的な前提が正しければ非常に強力ですが、逆に前提がズレていると、それに基づいた提案もズレるということ。
つまり、AIに任せてよいのは「ロジックの展開」や「アイデアの整理」までで、最終判断や仮説の妥当性チェックは、人間の役割だということです。
ChatGPTは「仮説づくりの相棒」として非常に頼りになりますが、データの裏にある感情や市場の肌感覚、競合の動き、社内リソースの事情など、非構造的な要素には弱い。
たとえば、InstagramのCPAが下がったのにCV数が減ったとき、ChatGPTは「クリエイティブの訴求軸を見直すべき」と言いました。しかし現場での実感としては、季節性の影響が大きく、そもそも検索量が落ちていた。これはAIには見えにくい要素です。
✅ AIは意思決定の「補助装置」であり、意思決定者ではない
だからこそ、ChatGPTに対しては「聞きすぎない」「依存しすぎない」ことが大事だと実感しています。
逆に、自分の判断を言語化して確認する手段としては、これ以上に優れたツールはないとも感じました。
精度を高めるプロンプト設計の重要性
ChatGPTを使いこなすうえで最も重要なのは、プロンプト(入力文)の設計力です。
広告予算配分に限らず、生成AIを業務に使う際には、以下のような考え方が有効です。
プロンプト設計の4つの要素
- 目的の明確化:何を出力させたいのか?(例:予算配分の改善案)
- 背景の共有:現状の課題や前提条件を説明(例:InstagramのCPAが高騰している)
- 制約条件の明示:守るべき予算、使える媒体、KPIなど(例:月間300万円、3媒体)
- 出力形式の指定:箇条書き・表形式・施策リストなど(例:表で比較して出して)
例えば、ただ「広告予算の最適化を教えてください」と聞くのと、
「以下の条件をもとに、広告予算の最適な配分案を表形式で提示してください。
- 月間予算:300万円
- 使用媒体:Google広告、Instagram広告、YouTube広告
- 目的:LTV最大化
- 制約:CV数は現状より落とさないこと」
と聞くのでは、返ってくる答えの精度と実用性はまったく違います。
また、ChatGPTは一度に完璧な回答を出せるわけではありません。
一度のプロンプトで得た出力に対して、以下のような再質問を繰り返すことで精度を高めていきます。
- 「その配分案の根拠を詳しく説明してください」
- 「Instagramの配分比率を30%から40%にした場合の想定効果を教えてください」
- 「ペルソナAへの訴求が弱くなるリスクはありますか?」
このように、ChatGPTとの対話自体が思考のプロセスとなり、結果的に判断の質が高まるのです。
✅ 良いプロンプトは、思考を構造化し、意思決定をスムーズにする
ChatGPTの真価は、「正しい答えを出すこと」ではなく、「問いの質を高めること」にあります。
私たちマーケターが問うべきなのは、「何をするか」ではなく「なぜ、それをすべきか」。
その問いを見つける力が、プロンプト設計には求められています。
次章では、他のAIツールとChatGPTをどう使い分けるか、そしてこれからの広告運用の展望についてまとめていきます。他のAIツールとの使い分けと今後の展望
ChatGPTとGoogle広告の最適連携
「ChatGPTは便利そうだけど、Google広告のスマート機能とどう違うの?」
こういった質問を受けることが増えてきました。
実際、Google広告には自動入札、レスポンシブ広告、パフォーマンス最大化キャンペーンなど、AIによる自動最適化機能が多数搭載されています。では、わざわざChatGPTを使う意味はあるのか?
結論から言うと、役割がまったく異なります。
Google広告のAIは「実行と最適化」に強く、ChatGPTは「設計と戦略思考」に強い。
これを明確に分けて考えることで、両者は非常に相性の良いツールになります。
例:使い分けの具体的なイメージ
| 項目 | ChatGPTの役割 | Google広告のAIの役割 |
|---|---|---|
| ターゲット層の仮説構築 | ユーザー行動や心理を対話で整理 | 過去データから類似ユーザーを抽出 |
| 予算配分の方針設計 | 配分案の根拠を整理し、選択肢を言語化 | 実行中に最適化(例:高CV面に多く投下) |
| クリエイティブの方向性決定 | 訴求軸やペルソナに応じた案を複数出力 | テストパターンを自動で配信 |
| 社内レポート作成・説明用の整理 | 意図や仮説を文章で明確化 | 数値の変化をダッシュボードで可視化 |
私がChatGPTを特に活用しているのは、媒体ごとの「戦略目的の再定義」の場面です。
たとえば、Google広告では自動入札に任せるとはいえ、「そもそもこのキャンペーンは何のために走らせているのか?」という視点が曖昧だと、施策自体が迷子になります。
このときChatGPTに、
「このプロダクトの認知獲得と顧客育成を目的に、Google広告のどの機能を使えばいい?」
「検索連動型広告とディスプレイ広告の役割を、ペルソナ別に分けて整理して」
といった具合に問いかけると、思考の枠組みがスッキリ整理され、結果的に施策実行フェーズで迷わなくなるのです。
✅ Google広告=操作と実行のAI/ChatGPT=構想と論理のAI
この両者を、対立ではなく「思考と実行のセット」として連携させること。
これが、これからの広告運用者に求められるスキルだと私は考えています。
今後の広告運用におけるAI活用の可能性
最後に、少し未来の話をしましょう。
私はこれまで、ChatGPTを使って多くの広告予算配分や戦略設計に関わってきました。使い込むほどに実感するのは、AIは広告運用の「型」を進化させているということです。
これまでの広告運用は、経験や勘、地道なA/Bテストに支えられてきました。
もちろんその重要性は変わりませんが、今後は以下のような流れが主流になるでしょう。
今後のAI×広告運用の主な進化ポイント
- 戦略フェーズのAI補助が当たり前に
→ ChatGPTで仮説設計・訴求整理・媒体選定を高速化 - 人間は「判断と調整」に集中する形へ
→ AIが案を出し、人間がリスクと戦略を擦り合わせる - AI間連携が実務を変える
→ ChatGPTとGoogle広告、GA4、CRMツールなどのAPI連携が進むことで、「言葉」で全体戦略が設計できる世界へ - チーム全体の思考の質が底上げされる
→ AIによってミーティングや企画書の前提が整理され、より建設的な議論が可能に
つまり、広告運用は「作業」から「思考設計」に進化するということです。
マーケターはもう、全部を自分で計算して、全部を細かく調整する必要はありません。
その代わり、AIの出力に「問いをぶつける力」や「判断軸を持つ力」が求められる時代になっていく。
私が日々感じるのは、AIはマーケターの仕事を奪うどころか、より創造的にしてくれるという確信です。
ChatGPTをはじめとした生成AIは、広告運用の実務を変えるツールではなく、思考の質を上げるレバレッジ。
それをどう使いこなすかが、今後のマーケターの価値を左右すると思います。
これからAIを取り入れていく方に、私から伝えたいのはひとつだけ。
「まずは聞いてみる。それが、すべてのはじまりです。」

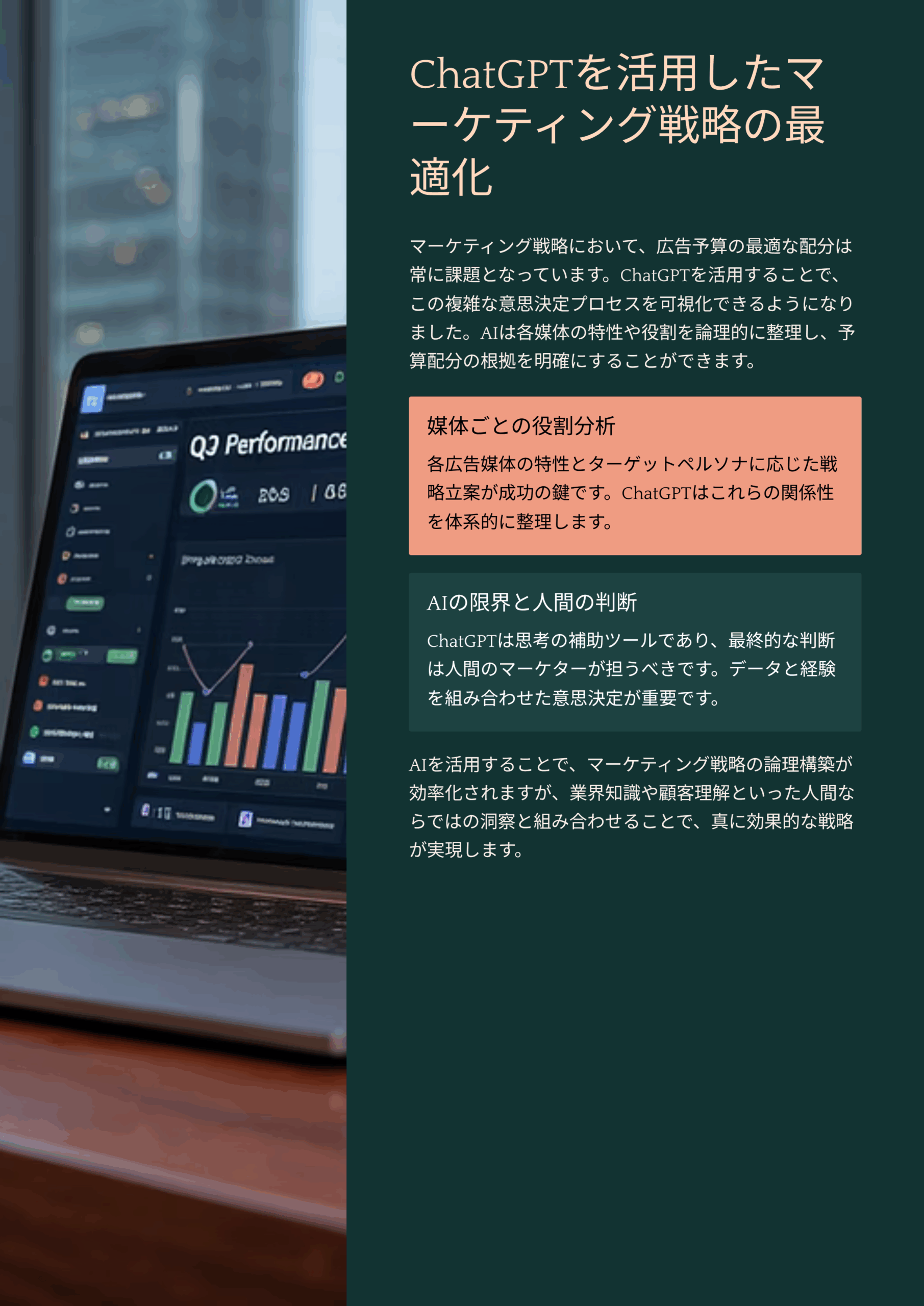









コメント