マーケティングを始めたいのに、何から手をつければいいか分からない——そんな経営者の悩みを、90日間で解決する実践ロードマップです。目次を見て必要なところから読んでみてください。
マーケティングの悩みはどこから来るのか
なぜ多くの経営者は「何から始めれば?」で止まるのか
「正直、マーケティングって何から手をつけていいのかわからないんですよ」
これは、先日ご相談いただいた、社員10名ほどの製造業を経営する50代の男性社長の言葉です。創業30年、下請けから脱却して自社製品を展開したいと考えているものの、何をすれば成果に結びつくのか分からず立ち止まってしまっていました。
これは決して珍しい話ではありません。私たちプロフェッショナルマーケティング株式会社にも、「まず何をすればいいの?」というご相談が年間で300件以上寄せられます。
ではなぜ、経営者の多くがこの「入り口」で止まってしまうのか。
それは、“マーケティングとは何か”が自分ごととして整理されていないからです。
学校で習ったわけでもなく、周囲に相談できるプロがいるわけでもない。しかも「マーケティングは大事だ」というプレッシャーだけはどこからともなくやってきます。
その結果、
- 本を読む
- SNSを始めてみる
- 広告を出してみる
といった断片的な行動をとっては、手応えがないまま「やっぱりうまくいかない」と悩み続けるのです。
しかし、問題は経営者の能力ではありません。「順番」と「考え方」がわかっていないだけなのです。
情報過多と専門用語が混乱を生む
現代は情報が多すぎます。検索すれば、「マーケティング戦略」「SEO」「SNS運用」「カスタマージャーニー」「コンテンツマーケティング」など、見慣れないカタカナと横文字の波が押し寄せてきます。
先ほどの製造業の社長も、ある程度は本やブログを読んでいましたが、こんな状態でした。
- 言葉の意味は何となくわかる
- けれど、それが「自社にどう関係するのか」がわからない
- だから行動に落とし込めない
これは「知識の断片」は得ているけれど、「設計図」がない状態とも言えます。
✅マーケティングが難しいと感じるのは、知識不足ではなく、構造を知らないからです。
ここで必要なのは、たった一つの問いを立てること。
「自分たちは、誰に、どんな価値を届けたいのか?」
この問いに明確に答えられれば、情報の取捨選択ができ、行動の優先順位も自然と見えてきます。
私、柳井弘幸も20年前、初めて自社のマーケティングに取り組んだときは、まさにこの「カオスの中で動けない」状態を経験しました。書籍や講座に手を出しては挫折の連続でした。
しかし、あるとき原点に立ち返り「誰に、何を、なぜ届けたいのか?」という問いに時間をかけて向き合ったことで、戦略も行動も一気に明確になりました。
マーケティングは、知識の積み上げではなく、設計と実践の連動です。
ここを押さえれば、「何から始めれば?」という悩みからは確実に抜け出せます。
次回は、その設計図の全体像を共有します。マーケティングの本質とは何か。それは“売るテクニック”ではなく、“伝えるための設計”です。続きを読み進めてみてください。
マーケティングの本質をまず理解する
「売れる仕組み」としてのマーケティングとは
「マーケティングって、結局どういうことなんですか?」
この質問も、経営者の方からよくいただきます。多くの方が、マーケティングを「広告の出し方」や「SNSの活用法」といったテクニックの集合体だと誤解しています。
けれど本来、マーケティングとは“売れる仕組み”をつくることです。
もっと言えば、「売らなくても売れていく状態」をつくる活動がマーケティングの本質です。
ある日、私のもとを訪れた40代の女性経営者。オーガニック食品の小さなブランドを立ち上げたばかりでしたが、なかなか売上が伸びず、焦りを感じていました。
「SNSも広告もやっているのに反応がないんです」
そこで私はこう尋ねました。
「“誰に”“なぜ”“それを届けたいのか”は明確ですか?」
しばらく沈黙のあと、「…実は、まだそこまで考えられていません」と答えてくださいました。
このように、行動より先に“設計”が必要なのです。
マーケティングの全体像は、以下のように整理できます。
| フェーズ | 内容 |
|---|---|
| 市場理解 | 顧客ニーズ、競合分析、自社の立ち位置を把握する |
| 戦略設計 | 誰に・何を・どうやって届けるかの骨組みを決める |
| 実行 | 商品開発、価格設計、販促、広告、営業活動など |
| 検証と改善 | 効果測定を行い、戦略をアップデートする |
✅つまり、マーケティングは断片的な手段ではなく、一連の流れです。
この流れが自社にとってどうあるべきかを設計することが、すべてのスタートです。
営業との違い・広告との違いを整理する
もうひとつ、混乱を招きやすいのが「マーケティング」と「営業」「広告」の違いです。
簡潔に整理すると、以下のような関係になります。
| 項目 | 主な役割 | 主体 | ゴール |
|---|---|---|---|
| マーケティング | 売れる仕組みの設計 | 経営・戦略担当 | 顧客を惹きつけ、自然に選ばれる状態をつくる |
| 広告 | 認知・興味喚起 | マーケ部/外部パートナー | 商品やサービスを知ってもらう |
| 営業 | 直接販売・クロージング | 営業担当者 | 顧客と対話し、契約・購入につなげる |
つまり、マーケティングは「広告」や「営業」を支える土台です。
広告だけをやっても、その下にマーケティングの設計がなければ、「誰に伝えたいのか」「何を伝えるのか」が曖昧になります。すると、広告費をかけても成果が出にくくなります。
また、営業活動も同様です。マーケティングで事前に“欲しい人”を集めておくことができれば、営業の効率は劇的に上がります。
私たちのクライアントでも、マーケティング設計をしっかり行ったことで、月10件だった問い合わせが月70件に増えた事例があります。結果、営業担当が「売り込む」必要がなくなり、「説明すれば自然に決まる」状態になったのです。
✅マーケティングは、「広告をうまく打つこと」や「営業がうまいこと」を意味しません。それらを“機能させる”ための設計が、マーケティングなのです。
この視点を持つことで、あなたの頭の中にあった霧が少し晴れたのではないでしょうか。
次の章では、いよいよ「初心者がまずやるべき具体的な3ステップ」をご紹介します。
「何から始めれば?」という悩みを、「これからこれをやればいい」と言える状態に変えていきましょう。
マーケティング初心者が取るべき最初の3ステップ
マーケティングを学び始めると、多くの方が「何から始めればいいのか…」と圧倒されます。
でも安心してください。マーケティングには、初心者でも着実に踏み出せる基本ステップがあります。
ここでは、私が20年以上マーケティングの現場で培ってきた経験をもとに、最初にやるべき3つのことをお伝えします。
このステップを踏むことで、「とにかく何かをやらなきゃ」と焦ってバラバラに行動するのではなく、成果につながるマーケティングの土台ができあがります。
現状把握:誰に・何を・どう届けるかの整理
マーケティングの出発点は、自社の現在地を正確に把握することです。
多くの中小企業が、「どんな商品を売りたいか」ばかりに目を向けがちですが、それでは的がぼやけてしまいます。まずは、次の3つを整理してみてください。
- 誰に届けたいのか(ターゲット)
- 何を届けたいのか(提供価値・商品)
- どうやって届けたいのか(チャネル・手段)
例えば、ある地元工務店が「自然素材の家づくり」を売りにしたいと考えていたとします。
この場合、
- 誰に?:30〜40代の子育て世代
- 何を?:安全で健康に良い、長く住める家
- どうやって?:自社サイト・Instagram・口コミ
この3つが見えてくると、広告の打ち方も、営業の言葉も、ホームページの構成も変わってきます。
✅マーケティングは「戦略的な自己紹介」から始まる、と言ってもいいかもしれません。
顧客視点で価値を定義し直す
次にやるべきことは、「自社の売り」を、顧客の目線で言い直すことです。
多くの企業が、自分たちのこだわりや技術を語りますが、それだけでは顧客の心に響きません。
たとえば、先ほどの工務店が「無垢材を使用しています」とPRしても、それが「どう嬉しいのか」が伝わらなければ価値にならないのです。
ここで必要なのは、「それがあることで、お客様の生活がどう変わるのか?」という視点です。
- 「無垢材=肌触りがよく、子どもにも安心」
- 「通気性の良さ=結露が少なく、アレルギーのリスクを軽減」
など、機能ではなくベネフィットで語るようにしましょう。
この変換は簡単ではありませんが、ここを乗り越えることで、あなたの商品やサービスは“選ばれる理由”を持つようになります。
自社の強みをコンパクトに言語化する
最後のステップは、自社の「らしさ」「違い」を、短い言葉で言い切ることです。
これは、「キャッチコピー」や「タグライン」のように派手な言葉である必要はありません。むしろ、誠実でわかりやすく、一貫性があることが大切です。
実際、当社が支援してきた企業の多くも、次のようにシンプルな言語化を行って成果を出しています。
- 「中小企業専門の財務パートナー」
- 「地方で働くママのためのオンライン塾」
- 「古民家を再生する設計事務所」
このように、自社の立ち位置を10秒以内で説明できるようになると、マーケティング活動すべてに軸が生まれます。
✅「何屋さんですか?」と聞かれたときに、迷わず答えられる状態を目指しましょう。
この3ステップを踏むだけで、あなたのマーケティングは格段に整理され、成果につながる動きに変わっていきます。
焦らなくても大丈夫です。大切なのは、「売る前に、伝える準備をする」こと。
次回は、この基礎をもとに、90日間でどう実践していくかの具体的な行動計画をご紹介します。段階的に進めることで、無理なく、でも確実に成果に近づけるようになります。
90日で実践するマーケティング行動計画
ここまでのステップで、マーケティングの本質と、初心者が踏むべき基礎は理解できたはずです。
でも、「わかったつもり」で終わってしまっては意味がありません。
マーケティングの真価は“実践”してこそ。
そして、その実践には明確な「期間」と「やることの順番」が必要です。
そこで私が推奨しているのが、90日間のマーケティング行動計画です。
この期間で大きな売上を狙うわけではありません。
むしろ、「顧客に価値を届ける仕組みの土台」をつくることが目的です。
では、どのような流れで進めればいいのか?
3つのフェーズに分けて、順を追って説明していきましょう。
第1フェーズ(1〜30日):市場と顧客を知る
このフェーズの主眼は、「自分たちが誰に、どんな価値を届けるべきか」を明確にすることです。
多くの企業がこの工程を飛ばして、「すぐに売る」ことに走りがちです。ですが、“誰に届けるか”を間違えると、何をしても反応が薄いのがマーケティングです。
まずは、次のような行動を取ることから始めましょう。
- 過去の顧客にヒアリングを行う(電話・対面・メール)
- 競合他社のホームページやSNSを分析する
- 自社の売上データを見て、「よく売れているもの」「繰り返し買ってくれている顧客」を把握する
- 業界の市場調査レポートを読んで、トレンドを掴む
この時期に大切なのは、仮説よりも事実に触れることです。
たとえば、あなたが「若い女性向けの商品」と思っていたサービスが、実際には「40代女性」がリピーターになっていることもあります。
✅売る前に、まず知る。知ることで、見える景色が変わります。
第2フェーズ(31〜60日):価値提案を形にする
次に行うのが、実際に「届ける価値」を明文化し、形にしていく段階です。
このフェーズで取り組むべきは、以下のようなことです。
- ペルソナ(理想の顧客像)を設定する
- USP(独自の売り)を言語化する
- 商品やサービスの紹介資料・説明文・キャッチコピーを作成する
- SNSやWebサイトで発信を開始する
- スモールテストとして、お試しの広告や投稿を実施する
この時期は、「完璧」を求めすぎないのがポイントです。
完璧を目指すと動きが止まり、「やってみないとわからない」本質から遠ざかるからです。
実際、ある士業のクライアントはこのフェーズで
「中小企業専門のオンライン相談窓口」という切り口を打ち出し、
30日後には月に5件の新規問い合わせを獲得できるようになりました。
✅重要なのは、「価値がある」と思っていることを、実際に伝えてみること。そこから反応を拾っていきます。
第3フェーズ(61〜90日):検証と改善を回す
最終フェーズでは、これまでの発信や行動に対して、「何がうまくいったか/いかなかったか」を見える化し、改善を加えるフェーズです。
ここでのポイントは、「数字」と「声」を拾うこと。
- SNSの投稿に対する反応(いいね・コメント・保存数)
- 問い合わせ内容や反応率(メールの開封率、CVRなど)
- 顧客からのフィードバック(感想、クレーム、質問)
たとえば、Instagramで投稿しても反応が薄い場合、
「デザイン」ではなく「メッセージ」がズレていることがあります。
また、「売れていない」と思っていた商品が、実は広告の出し方や掲載順が原因で、内容自体は高評価だったというケースもあります。
この時期にやるべきことは、以下のとおりです。
- 反応の高いコンテンツの特徴を分析し、量産化
- 反応の薄いものは原因を仮説立てて改善
- 顧客の声を反映し、商品の見せ方や価格を調整
- 効果があった施策をテンプレート化し、繰り返せるようにする
✅マーケティングは、最初から当てるものではなく、当てにいく仕組みをつくること。
この“検証と改善のループ”が、自走できる仕組みへとつながっていきます。
まとめると、90日間でやるべきことはこうなります。
| フェーズ | 期間 | 主な目的 | やること |
|---|---|---|---|
| 第1フェーズ | 1〜30日 | 顧客理解と市場把握 | ヒアリング、競合分析、自社分析 |
| 第2フェーズ | 31〜60日 | 価値の言語化と発信 | ペルソナ設定、発信内容作成、スモールテスト |
| 第3フェーズ | 61〜90日 | 検証と改善の習慣化 | 分析、改善、再テスト、仕組み化 |
マーケティングは「才能」ではなく、「プロセス」です。
この90日を踏み切ることで、あなたは“何となく手探りだったマーケティング”から、“仕組みで回すマーケティング”へと進化していけるはずです。
焦らず、でも止まらずに。
一歩一歩、価値を届ける仕組みを、あなた自身の手で育てていきましょう。
小さな成功体験がマーケティングを加速させる
マーケティングの道のりは、決して一足飛びではありません。
派手な成果や急激な売上アップに目を奪われがちですが、最初の一歩は、たったひとつの「反応」から始まります。
その「反応」をどう捉えるか、どう育てていくかこそが、マーケティングを継続し、加速させるための分岐点になります。
初めての問い合わせ・反応をどう捉えるか
「投稿に“いいね”が1件つきました」
「初めてWebサイトから問い合わせがきました」
このような些細な出来事に、どれだけの価値を見出せるか。
ここに、マーケティングを続けられる人と、途中で諦める人の違いがあります。
私のクライアントでも、ある飲食店経営者が最初にSNSで発信を始めた際、最初の1ヶ月は反応がほとんどありませんでした。
でも、ある日、たった1件のDMが届いたのです。
「今度の週末、子どもを連れて行きたいです。予約できますか?」
それを聞いたとき、彼の表情が一変しました。
「“誰かに届いた”という実感が、こんなに嬉しいものだとは思わなかった」と。
✅マーケティングにおいて、最初の反応こそが“信号”です。
それは単なる数字ではなく、「伝えたことに対するリアルな返答」であり、価値の兆しです。
たとえ1件でも、その裏には同じニーズを持った人が10人、100人と存在する可能性があります。
その1件を深く掘ること。なぜ反応したのか? 何に響いたのか?
それが次の打ち手を決めるヒントになります。
継続的改善の視点を持つ重要性
マーケティングがうまくいかない最大の理由は、“やめてしまうこと”です。
どんなにセンスがある人でも、継続と改善を繰り返さなければ、成果にはつながりません。
逆に言えば、継続できる人は、たとえ最初は下手でも、必ずマーケティングが「資産化」していきます。
では、どうすれば継続できるのか?
それは、「改善する前提で始める」ことです。
- 投稿が伸びないのは失敗ではなく、仮説が違っただけ
- 広告が成果につながらなかったのは、ターゲットがずれていた可能性
- 反応がない資料は、言葉が専門的すぎたのかもしれない
このように、「うまくいかなかった」を学びの種として捉えられると、改善の余地が無限に広がります。
たとえば、次のような「ミニPDCA」を1週間単位で回すのも効果的です。
- Plan(計画):今週は30代女性向けに投稿をしてみる
- Do(実行):Instagramで3件投稿
- Check(検証):どの投稿が最も反応があったかを確認
- Act(改善):次週は反応が高かったトーンで投稿を増やす
このように、マーケティングを「実験」として捉えることができると、日々の取り組みが楽しくなります。
✅マーケティングは、「正解を当てるもの」ではなく、「正解に近づく行動の積み重ね」です。
小さな成功体験が、マーケティングの燃料になります。
・最初の反応
・最初の問い合わせ
・初めての感謝の声
これらは、まだ売上に直結しないかもしれません。
けれど、それこそが「お客様との関係性が始まった証拠」です。
この積み重ねが、やがてブランドになります。信用になります。選ばれる理由になります。
だからこそ、小さな成功をバカにせず、ひとつひとつを丁寧に見つめ、育てていく姿勢が大切です。
マーケティングは、感動の連続です。
その最初の1つを、ぜひあなた自身の手でつかんでみてください。
よくある質問とその答え(Q&A形式)
マーケティングを始めようとすると、必ずといっていいほど出てくる「現実的な悩み」。
「うちには予算がない」「専任担当がいない」「そもそも自分が苦手」——
そんな声に、私 柳井弘幸がこれまで多くの現場で受けた質問をもとに、現実に即した視点でお答えします。
予算がなくても始められる?
答え:はい、むしろ予算がないときこそ、マーケティングの考え方が武器になります。
マーケティング=広告費、というイメージが先行しがちですが、本質はそこではありません。
本質は「誰に、どんな価値を、どう届けるか」という設計の話です。
この設計には、お金はかかりません。
時間と思考、そしてお客様と向き合う姿勢があれば、無料でもできることはたくさんあります。
✅予算ゼロでも始められるマーケティング行動例:
- 過去の顧客に電話やメールでヒアリング
- 無料で使えるSNS(Instagram、X、YouTube)で発信
- Googleビジネスプロフィールの登録・改善
- 自社の強みやストーリーをまとめたスライド資料の作成
- 無料の競合分析ツール(Ubersuggestなど)を活用して情報収集
たとえば、ある地域密着型の英会話教室は、広告費ゼロでInstagramを週3回更新し続けた結果、半年で月の体験予約が10件→35件に増加しました。
必要なのは「広告費」ではなく、「継続的に価値を届ける意志」です。
マーケティング担当がいなくても大丈夫?
答え:はい、大丈夫です。ただし、誰かが“意志を持って”担う必要はあります。
中小企業や個人事業主にとって、「専任のマーケティング担当」を置くのは難しいことが多いでしょう。
でも、マーケティングは“部署”ではなく“姿勢”です。
つまり、社長自身が最初のマーケターになってもいいのです。
実際、私が支援している企業の多くが、最初は社長がSNSを更新し、顧客の声を集め、商品説明の言葉を考えています。
もちろん、すべてを1人でやる必要はありません。以下のような“兼任マーケター”のかたちも有効です。
- 総務や広報が週に1回SNSを更新
- 営業が訪問時にヒアリングした顧客の声をまとめる
- アルバイトやインターンが発信文の下書きを担当
重要なのは、「誰が、どこまで、何のためにやるのか」を明確にしておくこと。
そして、マーケティングは一度始めれば少しずつ仕組み化できます。
投稿のテンプレート化、顧客対応のルール化、ツールの導入などにより、段階的に“自走”できるようになります。
✅マーケティングは「専門職」ではなく、「事業を育てる視点」。
社内の誰かがその役目を担えば、規模に関係なく機能します。
まとめ:お金も人も、完璧には揃わないのが普通です。
でも、それで諦める必要はありません。
むしろ制約があるからこそ、マーケティングの“本質”と向き合えるチャンスです。
少しずつ、できるところから始める。それが最も確実なスタートです。










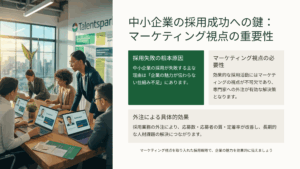
コメント