ChatGPTを広告運用にどう活かせるのか?試行錯誤の中で見えた可能性と限界を、実体験ベースで詳しく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
ChatGPTで広告運用の課題分析をして気づいた本質
ChatGPTを広告運用に使ってみた背景と狙い
「運用型広告のPDCAが思うように回らないんです」
中堅のWeb広告代理店に勤める田中さん(仮名)は、そう私に相談してきました。
毎月クライアントの広告レポートを提出してはいるものの、「何を改善すべきか」「どこに本当の課題があるのか」が曖昧なまま、運用が形骸化してしまっているといいます。
確かに、多くの現場で起きているリアルな課題です。
そんなとき、私たちプロフェッショナルマーケティングでも注目していたのが、ChatGPTの広告運用への活用でした。
「AIなら定量・定性の両面から広告運用の課題分析ができるのでは?」という仮説のもと、まずは自社案件に導入してみることにしました。
目的は明確です。
- レポート作成の効率化
- 改善点の仮説出し
- 競合との違いの明文化
- 担当者の視野拡張
特に期待していたのは、広告パフォーマンスの背後にある”構造的な課題”の発見でした。
人間の視点では見落としがちなパターンを、GPTが補完できるかもしれない。そんな可能性を感じていました。
想定していた効果と実際のギャップ
導入当初、私たちは正直「もっとすぐに結果が出るだろう」と思っていました。
ChatGPTにレポートを読み込ませ、「このキャンペーンの改善点は?」と聞く。
すると、構造的な課題までズバリ指摘してくれる——そんな未来を描いていました。
しかし、実際に得られた答えはこうです。
- 「LPのファーストビューの訴求が弱い可能性があります」
- 「ターゲット層のニーズと広告文のギャップがあるかもしれません」
- 「CV率の変化には曜日要因も考えられます」
言っていることは正しい。けれど、浅い。
すでに現場で把握している“当たり前の視点”にとどまり、それ以上の発見には至りませんでした。
そこで私たちはプロンプト(質問の投げ方)を大幅に見直しました。
単に「改善点は?」ではなく、
- 「直近3ヶ月のROAS推移に基づいて、構造的なボトルネックを特定してください」
- 「CVRが落ちている要因を、広告文・配信面・ターゲティング・LPの観点からそれぞれ仮説を出してください」
- 「競合広告との違いを、訴求軸とコピー表現の観点で比較してください」
このように、より多角的・構造的な視点を促す質問を行うことで、GPTの回答精度は明らかに向上しました。
結果的に得られた示唆は以下のようなものでした。
- 配信先メディアごとのCTRとCVRの乖離
- 広告文が顧客の“状態”に合わせられていない点
- 競合が使っている「数字×安心感」の表現の有効性
✅ このようなアウトプットは、これまで担当者が「感覚」で語っていた内容を、構造的に言語化する手助けとなりました。
私たちが気づいた最大のポイントは、ChatGPTは「問いの質」によって能力が劇的に変わるツールであるということです。
的確に問えば、驚くほど鋭い答えが返ってきますし、曖昧に問えば、平凡な内容しか返ってきません。
つまり、人間側の思考設計が必要不可欠なのです。
広告運用の本質的な課題分析は、単なるデータ分析ではありません。
数値の背後にある構造、顧客心理、競合の戦略を統合的に見抜く必要があります。
ChatGPTはその思考の「補助線」として非常に優れていますが、それ単体では答えにはたどり着けない。
この視点を持つことで、私たちは「AIを使って考える」新しいフェーズに入ることができました。
この気づきは、田中さんにも共有しました。
彼はChatGPTを、「仮説を広げる壁打ち相手」として活用するようになり、広告運用の質が着実に向上しています。
次章では、実際にChatGPTがどの領域で強みを発揮したのか、具体的に見ていきましょう。
ChatGPTが得意な広告運用分析の領域とは
キーワード抽出・競合比較の自動化
「毎回、キーワードリサーチに時間がかかりすぎるんです」
これは、社内の若手マーケターからよく聞く悩みのひとつです。
Google広告やYahoo広告、SNS広告など、媒体ごとに必要なキーワードは違いますし、それを競合と比較して最適化する作業は意外と泥臭く、時間もかかります。
そこで私たちは、ChatGPTを使って自動的にキーワードと競合の訴求軸を分析できないかを試してみました。
やり方はシンプルです。
- 自社と競合の広告文を複数提示
- 商材ジャンルやペルソナ情報をセットで入力
- 「この2者のキーワードや訴求の違いを分析してください」とプロンプト
すると、ChatGPTは以下のように整理してくれました。
- 自社:価格訴求、限定性(例:「今だけ」「初回無料」)が多い
- 競合A:成果ベネフィット(例:「〇〇できる」「〇〇を解決」)中心
- 競合B:信頼性や口コミ訴求(例:「97%が満足」「〇〇で紹介されました」)に強み
さらに、自社の広告文に足りない要素として、次のような提案もしてくれます。
- 「顧客が得られる具体的な結果を明示しましょう」
- 「限定オファーだけでなく、社会的証明も加えると信頼度が増します」
✅ このように、ChatGPTは「構造的に違いを整理する力」に非常に優れています。
キーワードだけでなく、言葉の使い方の傾向や“伝わり方のニュアンス”まで可視化できるのが大きな強みです。
私自身、競合のLPや広告を見比べて「何が違うんだろう」と感じることは多々ありました。
ですが、ChatGPTに一度整理してもらうだけで、比較の切り口が明確になるのです。
これは単なる時短ではなく、分析の質そのものを高めるアシストになります。
広告コピーの改善点指摘とその精度
次に試したのが、「既存の広告コピーをChatGPTに添削してもらう」という使い方です。
たとえば、以下のような広告文があったとします。
「今だけ限定!お得に始める〇〇キャンペーン実施中」
人間の目から見れば、よくあるパターンです。
でも、果たして本当に効果的なのでしょうか?
これをChatGPTに「改善点を3つ挙げてください」と投げると、次のような指摘が返ってきました。
- 具体性が欠けており、何がお得なのかが不明瞭です。例:「月額〇〇円OFF」などの数値訴求を追加すると効果的です。
- 「今だけ限定」はよく使われる表現で埋もれやすいため、差別化できるフレーズ(例:「9月末までの3週間限定」)にすると注目度が上がります。
- ベネフィット(顧客が得られる価値)が曖昧です。「〇〇の悩みを最短3日で解決」など、成果ベースの訴求を追加するとクリック率が上がります。
これを見た時、私たちは「確かに」と膝を打ちました。
✅ ChatGPTは、広告コピーの「テンプレ感」や「抽象性の罠」に気づかせてくれます。
しかも、このような指摘は論理的で納得感があるため、社内のチーム内でも「なるほど」と共通認識が生まれやすいのです。
さらに応用すると、次のような指示も可能です。
- 「20〜30代女性向けに感情的訴求を強めたコピーにしてください」
- 「BtoB商材向けに信頼性重視のコピーに言い換えてください」
- 「30文字以内でクリック率が高そうなタイトル案を3つ出してください」
こうした「文脈+制約条件」にも柔軟に対応できるのが、ChatGPTの真骨頂です。
もちろん、最終的な判断や表現の仕上げは人間の役割ですが、コピーの初稿段階で「ここまで出せる」のは非常に価値が高いと感じています。
次章では、逆に「ChatGPTでは難しい」と感じた領域について、率直にお話しします。
活用を通じて浮き彫りになった限界と注意点
数値データの扱いと解釈の課題
ChatGPTは言語処理に特化したAIです。
そのため、数値の計算や精密な統計分析に関しては得意ではありません。
実際に私たちが試したケースでは、広告のパフォーマンスレポート(例:CVR・CTR・ROASなど)を読み込ませ、
「問題のあるキャンペーンを特定してください」と投げかけました。
すると返ってきたのは、
- 「CVRの低下が見られるキャンペーンBは改善対象と考えられます」
- 「ROASが最も低いものはCであり、投資対効果の見直しが必要かもしれません」
確かに、数値の比較としては正しい。
しかしここで大事なのは、“なぜその数値になっているのか”という因果関係の深堀りです。
問題はこの先。
「なぜCVRが下がっているのか?」と問うと、
- 「広告文が訴求力に欠ける可能性」
- 「ターゲティングが広すぎる可能性」
- 「LPの構成が直帰を招いている可能性」
といった一般論にとどまる回答が多くなります。
つまり、数値そのものの扱いはできても、データの背景を読む“解釈力”は限界があるのです。
また、表やグラフを使ってのビジュアルな分析にも不向き。
CSVを投げても構造を正しく読み取れなかったり、意図とズレた仮説を返してくることもあります。
✅ 私たちが辿り着いた結論は、「ChatGPTに数値を渡す際は、人間が前提と文脈をしっかり与えることが不可欠」ということ。
たとえばこんな使い方が有効です。
- 「この3つのキャンペーンの中で、CVRの変動に注目してどこに異常があるかを分析してください。特にターゲット属性の違いに注目してください。」
- 「月別のROAS推移から、外部要因(季節性や競合の動き)を加味して仮説を出してください。」
このように、背景や視点を先に人間が設計することで、GPTの分析精度は大きく変わります。
つまり、数値を読むのはAIでも、意味を与えるのは人間の仕事だということです。
クリエイティブ領域での誤認識リスク
もうひとつ、使っていて感じた限界がクリエイティブ表現の認識力です。
たとえば、あるLP(ランディングページ)の構成について「良い点と悪い点を指摘してください」とChatGPTに頼むと、
次のような回答が返ってきました。
- 「ファーストビューにインパクトのある画像が使われていて良いです」
- 「CTAがページ下部にあり、遷移率を下げている可能性があります」
一見もっともらしく見えますが、実はこのLPには画像が存在していないんです。
ChatGPTはテキストベースの言語モデルなので、実際のビジュアルやデザインを正確に読み取ることはできません。
また、画像や動画広告のクリエイティブ評価についても、
- 「配色が明るく、ポジティブな印象を与えます」
- 「フォントが可読性に優れています」
といった“それっぽい”コメントは出てくるものの、本質的なユーザー体験に基づく評価とは言いがたい内容が多いです。
このようなケースは、現場経験がある人間なら直感的に見抜けるのですが、ChatGPTは“言語で表現されていない情報”を扱うのが苦手です。
さらに、SNS広告などで効果が左右される要因の多くは、
- 表情のニュアンス
- 空白の使い方
- スクロールの動線
- ユーザーの“流れ”の中での接触タイミング
など、言語では言い表せない「文脈と感覚」の領域です。
✅ ここで私たちが学んだのは、「AIは“伝わりやすさ”の補助線にはなるが、“伝わるかどうか”は人間にしか判断できない」という本質です。
つまり、ChatGPTはクリエイティブの方向性を検討する段階では役立ちますが、
最終的な判断やチューニングは、現場の人間の“感覚”にしかできないということです。
その結果、私たちのワークフローでは次のような役割分担をしています。
- ChatGPT:初稿の整理・改善提案・言語の最適化
- 人間:実際の訴求効果の検証・フィードバックの解釈・感情反応の把握
このように、AIに任せる領域と、人間が引き受ける領域を明確にすることで、
ChatGPTは広告運用の強力なパートナーになり得ます。
次章では、そうした「人とAIの最適な役割分担」について、より具体的に見ていきましょう。
人間×AIの最適な役割分担とは何か
人の視点が必要な部分とGPTで効率化できる部分
「これ、GPTに任せていいか迷ってるんです」
ある若手マーケターが、広告運用の月次レポートを作成中にそんな相談をしてきました。
彼は、ChatGPTがアウトラインまで作ってくれる便利さを感じつつも、「このまま提出していいのか」と不安を抱えていたのです。
その気持ち、よくわかります。
便利だけど、どこまで任せていいかが分からない——これは、多くの現場で起きている“AIあるある”です。
そこで私たちは、ChatGPTと人間の得意領域の違いを明文化しました。
まず、GPTが得意なのは以下のような領域です。
- 言語の整理・要約・言い換え
- パターン分析やテンプレート化された業務
- 既存情報をもとに仮説を広げる作業
- 初稿のアウトプットやアイデア出し
- 定型的な改善案の抽出
これに対して、人間が担うべきなのは次のような領域です。
- 現場文脈の理解と判断
- 顧客の温度感・心理変化の把握
- “言葉にならない違和感”の検出
- 意思決定と責任の所在
- 新しい価値の創造や発想の飛躍
例えば、広告のCTRが落ちていたとしても、
「数字の変動をどう解釈するか」は担当者の感覚や経験に大きく依存します。
GPTはその変動を機械的に読み取り、「可能性のある要因」を並べることはできますが、
“今この状況で何を選ぶべきか”の判断はやはり人間にしかできません。
また、クライアントの置かれている状況や、過去の施策の積み重ねなど、GPTが持ち得ない文脈情報は、人間が補完する必要があります。
このように、GPTは“材料出し”や“整理”には強く、
人間は“意味づけ”や“決断”にこそ価値を持っています。
この役割の違いを理解することが、AI活用の最初の一歩になります。
実務での使い分けルールの具体例
では、実際の業務でどのようにGPTと人間の役割を使い分ければ良いのでしょうか?
私たちは、社内で以下のような使い分けルールを設けています。
1. ChatGPTに任せるタスク
- キーワードリサーチの初期整理
- 競合広告の訴求比較
- 広告文の改善案出し
- LP構成の要素整理
- 提案資料の骨子作成
- 数値レポートの要点要約(※判断は人が行う)
2. 必ず人間が最終判断を行うタスク
- 広告戦略の設計・見直し
- ターゲティングの最適化
- 数値変動の解釈と施策立案
- クライアントへの提案内容決定
- クリエイティブの方向性選定
たとえば、広告文の改善に関しては、
- ChatGPTが初稿を5案出す
- マーケ担当者がその中から2案を選び、ニュアンスを調整
- クリエイティブチームが最終的なトーンを整える
このように「段階的に人の視点を入れることで、AIの出力がチーム全体の生産性に繋がる」フローが出来上がりました。
✅ 特に重要なのは、「AIに任せるときは、目的と条件を明確に伝えること」。
「30〜40代の男性向けに、ビジネス系商材の広告文を3案出して。信頼性重視で、数字を含めた訴求を使ってください」
このように明確にインプットを設定すれば、GPTは高い精度で応えてくれます。
逆に、「いい感じの広告文作って」と曖昧な指示をすれば、凡庸なアウトプットしか返ってきません。
このような使い分けのルールを浸透させることで、社内では「GPTは人を置き換える存在ではなく、“拡張する道具”である」という意識が根付き始めています。
特定の人しかできなかった仮説立てや分析業務が、誰でも一定の精度でできるようになったというのは、大きな変化です。
次章では、このような活用をどう社内に定着させ、業務フローに組み込んでいくかについてお伝えします。
ChatGPTを広告運用に組み込む方法【事例あり】
実際のワークフローにどう落とし込むか
ChatGPTの活用が「便利そう」で止まってしまう最大の理由は、現場の業務フローにうまく落とし込めていないことです。
導入当初、私たちの社内でもこうした声が上がっていました。
- 「誰が、いつ、どうやって使えばいいのかが曖昧」
- 「使ってみたけど、あとで人間が直してるなら二度手間じゃないか」
- 「そもそも、自分の業務にGPTが使えるか分からない」
そこで私たちは、ChatGPTの業務利用を「属人化」させないように、実際の広告運用フローの中に明確な“導入ポイント”を設定しました。
以下は、広告キャンペーンの立ち上げ〜改善までの流れの中で、ChatGPTを組み込んだワークフローの例です。
広告運用ワークフロー×ChatGPT活用ポイント
| 工程 | 人間の役割 | ChatGPTの役割 |
|---|---|---|
| 市場調査・競合分析 | 課題設定・視点の設計 | キーワード抽出、競合の訴求整理 |
| ペルソナ設計 | 顧客理解・仮説立て | 顧客のニーズ整理・共感ポイントの提案 |
| 広告コピー作成 | 最終判断・表現調整 | 初稿のたたき台生成、改善案提示 |
| LP構成案の設計 | ストーリーの骨格構築 | セクション構成のテンプレ提案 |
| 配信後の数値分析 | データの解釈・意思決定 | 数値の要約、改善点の洗い出し |
たとえば、ある化粧品ブランドの案件では、新商品の訴求軸を明確に定めるため、ChatGPTに以下のようなプロンプトを活用しました。
- 「30代女性で、肌荒れに悩むユーザーを対象に、商品Aの特徴を訴求する広告コピーを3パターン出してください」
- 「競合商品B・CのLP構成と比較し、差別化できる切り口を整理してください」
このように具体的な目的を持って使うことで、情報整理のスピードと精度が格段に向上しました。
大切なのは、「どの工程で、どんな成果物をGPTに任せるか」をあらかじめルール化しておくこと。
これにより、誰が使っても一定の成果を出せる体制が整っていきます。
社内活用・共有の進め方と壁
ただ、ChatGPTの導入がスムーズに進んだわけではありません。
私たちのチームでも、初期段階ではいくつかの“壁”にぶつかりました。
主な課題は以下の3つです。
- ①「なんとなく使って終わる」パターンの多発
- ② メンバー間で活用レベルに差が出る
- ③ 成果にどうつながったかが見えづらい
こうした課題を解決するために行ったのが、以下の3つの対策です。
1. GPT活用の「フォーマット」を標準化
たとえば、広告コピー改善のプロンプトを以下のように定型化しました。
- 「以下の広告文を、20代女性向けに感情的に書き換えてください。CV率を高める要素も加えてください。」
これにより、誰が使っても一定の質のアウトプットが得られるようになり、試行錯誤のムダが減少しました。
2. 社内「ChatGPT活用ミーティング」を定期開催
月1回、実際に使ってみた事例や学びをチームで共有する時間を設けています。
- 成功したプロンプト事例の紹介
- 逆に、うまくいかなかったケースとその要因の共有
- 業務別テンプレートの検討
✅ このような場を持つことで、“知見の属人化”を防ぎ、チーム全体の活用スキルが底上げされました。
3. 「GPTで何分時短できたか」をKPIにする
成果が見えづらいという問題に対しては、「時短効果」にフォーカスしました。
- 広告コピー作成:平均30分短縮
- 提案書の構成案作成:平均45分短縮
- 数値レポートの要点要約:平均20分短縮
これにより、定性的な価値を定量的に可視化でき、メンバーのモチベーションも向上しました。
よくある疑問とその答え(Q&A)
ChatGPTは広告代理店業務を代替できる?
これはよく聞かれる質問のひとつです。
「GPTがここまでできるなら、広告代理店っていらなくなるんじゃないか?」と。
結論から言えば、GPTは広告代理店業務の“すべて”を代替することはできません。
ただし、“一部の作業領域”については確実に代替、あるいは補完が可能です。
たとえば、以下のような業務はChatGPTで一定レベルまで対応できます。
- 広告コピーの初稿作成
- 競合分析の骨子出し
- キーワード整理や仮説の立案
- レポート文章の要約・整形
- 提案書の構成下書き
こうした定型化できる業務や、情報の整理が主なタスクについては、GPTが強力な助っ人になります。
しかし、次のような業務は人間の役割です。
- 顧客の表情や声色からニーズを読み取ること
- コンセプト設計や全体戦略の構築
- 実行プランを取捨選択する意思決定
- クライアントとの信頼関係構築
- ブランドの文脈に即したトーン設計
つまり、GPTは「やるべき業務」を代わりに考えるのではなく、「やると決めた業務」を効率よく進めるための補助ツールです。
✅ よく例えるのですが、ChatGPTは「優秀なインターン」のような存在です。
- 指示が具体的であればあるほど成果を出す
- 指示が曖昧だと間違えることもある
- 最終的な責任は社員(人間)が取る
だからこそ、人間側に「問いの力」と「判断の軸」が必要になるのです。
広告代理店の価値がなくなるのではなく、変化していく。
“作業”ではなく、“意味をつくる仕事”に集中するために、GPTをどう使いこなすかが問われています。
広告運用の成果にどれだけ影響する?
「実際、GPTを使ったら成果は上がるんですか?」
これも当然の疑問ですよね。
ここで重要なのは、GPTは“直接的な成果改善”というより、“間接的なパフォーマンス向上”を支援するツールであるという視点です。
私たちの運用現場で見えてきたのは、「考える時間」を減らし、「検証と改善の時間」を増やすことの価値です。
たとえば、以下のような成果が出ています。
- 広告文改善のスピードが2倍に
→ A/Bテストの回転数が増え、CTR改善につながった - レポート作成にかかる時間が50%削減
→ 空いた時間で配信面の見直しや新規提案にリソースを投入できた - 新人マーケターの初動クオリティが向上
→ ベテランが手直しする工数が減り、育成スピードが上がった
また、ある案件では、ChatGPTを活用してLP構成の仮説出しを行い、
「成果ベネフィット重視」→「共感訴求重視」に切り替えたことで、CVRが1.8倍に改善した例もありました。
ただし注意したいのは、GPTを“使いこなすスキル”が成果に直結するということです。
- 良いプロンプトを書く
- 出力結果を正しく解釈する
- 実行と検証を回すフローを整える
この3つが揃って初めて、GPTは広告運用の成果に寄与してくれます。
✅ GPTを使ったから成果が出るのではなく、GPTを“使う人の思考力”が成果を引き上げるのです。
AIは魔法ではありません。
でも、“賢く働く力”を一段階引き上げてくれるツールであることは間違いありません。
まとめ:ChatGPTで広告運用はどこまで進化するか
本質を見失わない使い方とは
ChatGPTは、広告運用において間違いなく「変化」をもたらすツールです。
それは、単なる自動化や時短にとどまらず、人間の思考や視点を拡張する可能性を秘めた存在だと、私自身の実体験から確信しています。
しかし同時に、この問いは常につきまといます。
「AIを使って、私たちは本当に“良い仕事”ができているのか?」
便利さや効率だけを追い求めていると、ユーザー視点やブランド文脈といった“広告の本質”を見失うリスクもあります。
広告とは、「誰に、何を、どう伝えるか」という人間同士のコミュニケーションの設計です。
AIはあくまでその補助線。判断するのは常に人間です。
✅ だからこそ、「なぜこの訴求を選ぶのか」「なぜこの表現が響くのか」を言語化し、GPTと対話できる人間力が求められます。
ChatGPTを使いこなすうえで、私が意識している“本質を見失わないための3原則”を共有しておきます。
- AIに頼りすぎない:「考える」を放棄しない
- 答えを求めず、「問い」の質を磨く
- ユーザーの感情と行動に責任を持つ
この3つを土台にすれば、GPTはただの“便利な道具”ではなく、思考と創造を支えるパートナーになります。
今後に向けた活用戦略の考え方
広告運用におけるAI活用は、今後ますます加速していくでしょう。
ChatGPTに限らず、動画生成、画像最適化、配信自動化といった領域でもAIの進化は目覚ましいものがあります。
その中で、私たちマーケターが取るべき戦略は「AIに置き換えられない仕事にシフトする」ことです。
では、それは何か?
私は次の3つだと考えています。
- 思考の設計
- 問いを立て、仮説を構築し、意味をつくる
- GPTを「どう使うか」をデザインする側に立つ - ブランド視点の統合
- 単発の成果ではなく、ブランド全体のストーリーを一貫して届ける
- タッチポイントごとに体験をつなげる設計力が問われる - 人の感情に深く共鳴する表現
- 心を動かす言葉、共感を呼ぶストーリーは、まだ人間の強み
- 感性と戦略を両立する表現者が価値を持つ時代になる
AIを恐れる必要はありません。
ただし、AIができることとできないことを見極め、自分の役割を再定義する必要はある。
私たちプロフェッショナルマーケティングでも、GPTの活用を進めながら、「考える力」「伝える力」「感じる力」という人間の本質的な能力をどう伸ばすかを、常に問い続けています。
✅ ChatGPTの時代においても、“人が考え、人が感じ、人が決断する”広告は、これからも価値を持ち続けます。
大事なのは、AIに使われるのではなく、AIを使って、自分の仕事の本質にもっと集中できる環境をつくること。
広告運用の進化は、ツールの進化だけで決まるのではありません。
それをどう使うか——その選択こそが、これからのマーケターの価値を決めるのです。

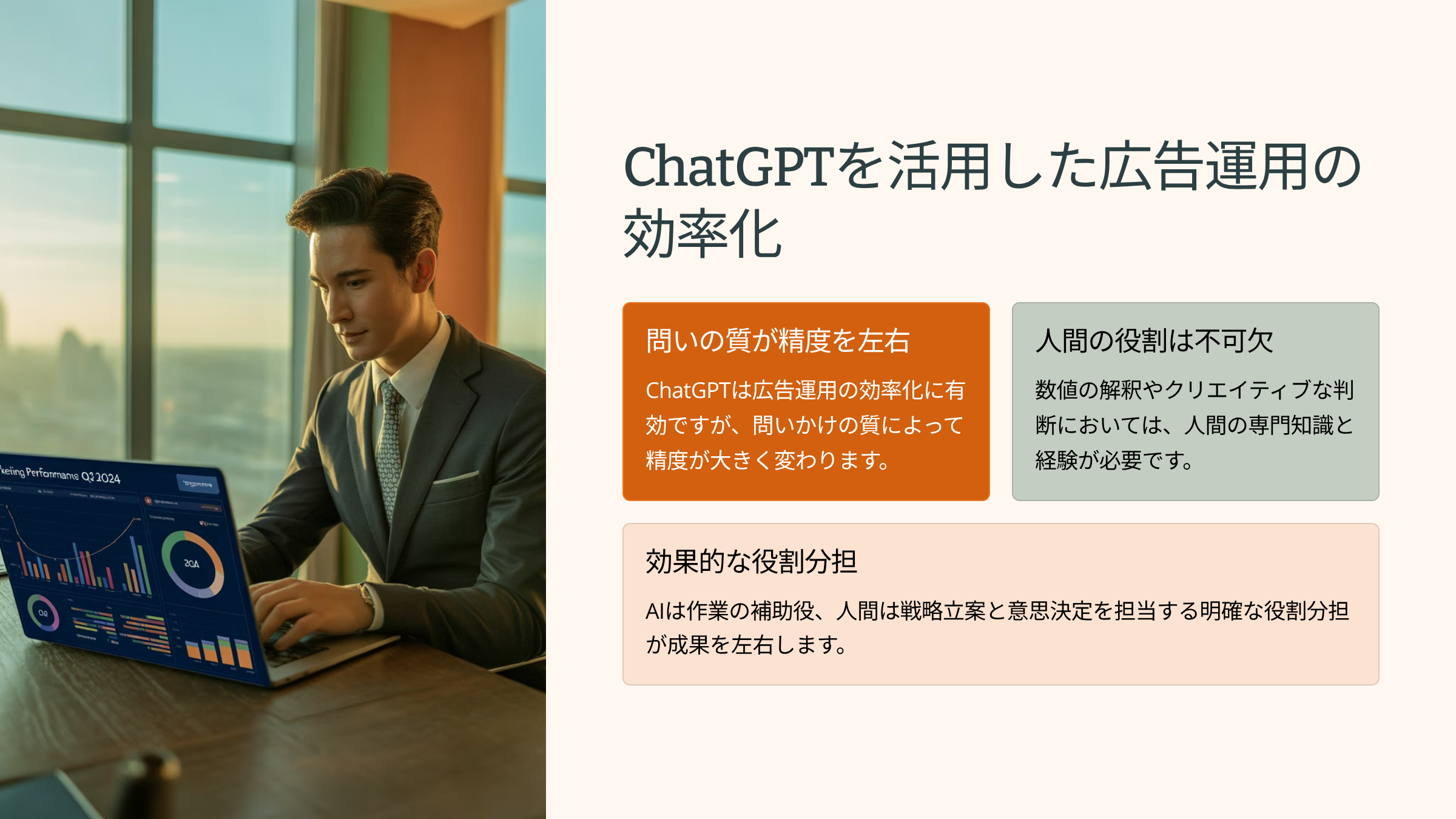








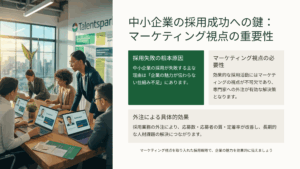
コメント